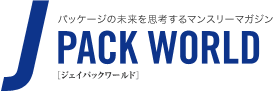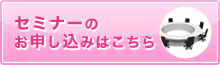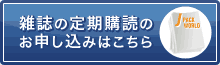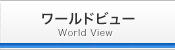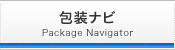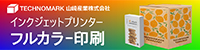トップページ > バックナンバー
-
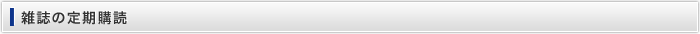
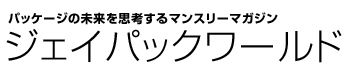
本誌は、新しい時代ニーズに応えうる商品開発のイノベーションを志向し、新しいマーケットの創出に挑戦するビギナーからプロまでの包装と関連実務者(食品、医薬品、工業、流通など)のための包装総合情報誌です。数十年の包装実務経験を持つ包装のプロフェッショナルが多数編集に参加し、その豊富な経験と知恵、さらには多彩なネットワークを生かし、充実した内容を目指します。今までの包装関連情報誌にはない、将来を展望した課題の提案や問題提起などプロフェッショナルならではの視点から、包装の未来を志向します。

〈発行日〉毎月15日
〈主な読者〉食品・医薬品分野を中心とした包装ユーザー、包装資材・機械メーカー、商社
〈形態〉本文(オールカラー)48ページ、A4変形判
〈価格〉26,800円(本体・送料込:24,364円+10%税)※年間購読の価格です。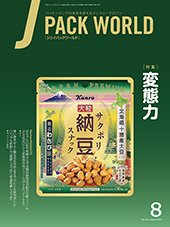
2025年8月号
【特集】
- ■変態力
唐突に「変態力」などと掲げると、「気でも狂ったか!?」と思われるかもしれない。ただ、蝉など昆虫には変態する能力を有する種も多く、変態は成長のステージに応じて自らを変えるとの意味が本来ある。
>>目次
当然、昆虫の変態とは異なるが、人生にもいくつかのステージがある。仏道修行では(1)学生期、(2)家住期、(3)林住期、(4)遊行期の四住期に分けるようだ。また「3・11」の震災やCOVID-19の感染流行などで、人生の転機を迎えた人などもいよう。
人生には必ず、執着心(惰性)を動揺させて疑いの心を生じ、変態をうながすことがある。心が変われば人が変わる。人が変われば生活が変わる。生活が変われば包装が変わる。
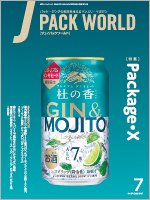
2025年7月号
【特集】
- ■Package・X
10年ほど前は「IoT」「I4.0」といっても、どこにも引っ掛からなかったが、現在では猫も杓子も「DX」「GX」「SX」と、何にでも「X」をつければよいまでになっている。あの「Twitter」でさえ、イーロン・マスクによって「X」と改名された。
>>目次
「何がいいのか?」と思いつつも、流れに逆らわずに「PX」をテーマに掲げてみた。「PX」とは、いわずもがな「Package・X」である。いまさらだが、なぜ「Transformation」を「X」に略すのかは、英語圏の慣習があり、日本人にはピンとは来ない。
「Trans」には「横断する」「超える」との意味があり、これが「Cross」の意味とシンクロするため、「Cross」の省略形の「X」で代替されるようである。かつてはまって観ていた米・テレビドラマ「Gossip Girl」の、アイコニックなキャッチフレーズが「XOXO, Gossip Girl」であった。
米・ニューヨークのUpper east sideを舞台に、ヤング・セレブたちの刺激的な世界を描いたテレビドラマである。こちらの略語の「XOXO」は習慣ではなく、主に手紙やメールなどの文章の締めに使われ、愛や友情を表現する際に用いられる、「Hugs and Kisses」のスラングである。「XOXO, J pack World」。
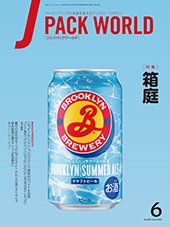
2025年6月号
【特集】
- ■箱庭
「箱庭」とは、「浅い箱に土砂を入れ、家や橋などの模型を置き、小さい木を植えるなど、山水の景色や庭園を象ったもの」である。江戸時代に流行した一種のジオラマで「涼を呼ぶもの」として俳句の夏の季語となる。
>>目次
小説家の高浜虚子の「箱庭の人に古りゆく月日かな」との句について、箱庭に置かれた人形を自身に見立てて詠んだとの解釈もある。
あの安倍晋三氏は、総理在任中に「地球儀を俯瞰する外交」を標榜していたが、そもそも地球儀は地球を俯瞰する道具である。箱庭にも俯瞰的な意味合いがあり、箱庭療法といったこともその一つであろう。箱庭で心象風景を探求し、自己の理解と癒し、成長に繋げる心理療法である。
また大人から子どもまで人気の「どうぶつの森」「マインクラフト」のようなデジタルゲームなども箱庭ゲームと呼ばれる。アナログでは、今でも人気の人生ゲームも箱庭の範疇ではなかろうか。包装もまた「箱庭」といえなくはない。
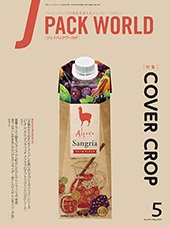
2025年5月号
【特集】
- ■COVER CROP
最近は「土」に関心が寄せられる。生命の起源であり、モノづくりの基盤であるからだ。いい換えれば、地球そのものへの関心である。土壌学者の藤井一至氏の「土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて」(光文社新書)などの著書も面白い。
>>目次
さて、「カバークロップ」(COVER CROP)との言葉をご存知であろうか。土壌浸食を防ぎ、土壌中に有機物を加え、土壌改良に役立つ作物の総称である。和訳すれば被覆作物となる。
カバークロップには土壌の物理性改善、センチュウの防除、天敵の保持・増殖など多くの機能がある。私見だが、稲作で田に水を張るのも「COVER WATER」で同じ原理ではないかと思う。近しいクリエイターは「紫外線から肌を守る化粧は性別に関係なく必須」というが、これは「COVER COSMETIC」である。
こうしたことからも分かるが、「COVER」とは単に命やモノを覆うだけでなく、被覆物の様々な自助作用を促すのである。
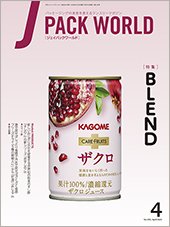
2025年4月
【特集】
- ■BLEND
サステイナブルを命題にモノマテリアル化が喧伝される。「モノ」(MONO)は「1つ」で、「ポリ」(POLY)は「たくさん」の意味で、確かにマテリアルリサイクルには、PETボトルのようにモノマテが最適ではある。ただ江戸の平賀源内もいうように「世間ってなあ、まぁ広い」わけだ。
>>目次
単純ではなく複雑、一様ではなく多様である。ましてダイバーシティなどが喧伝されるときに、なぜパッケージだけが「モノ化」が喧伝されるのか。そもそも目の敵のプラスチックはポリマーである。
むしろ自動車やウイスキー、コーヒーや米などハイブリッドにはじまり、複数多様な組み合わせの「用」こそが、人知の詰まった誇るべき技術とノウハウである。そろそろサステイナブルも辻褄が合わなくなってくるころである。
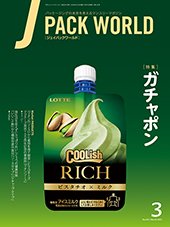
2025年3月
【特集】
- ■ガチャポン
再燃する「ガチャポン」「ガチャガチャ」は単なる擬音由来の愛称で、正式名称は「カプセルトイ」とのことである。とはいえ、もはや「単なる擬音」とはいっておれず、「ガチャポン」「ガチャガチャ」「ガチャ」のいずれも登録商標とのことである。
>>目次
江戸中期に異彩を放った平賀源内でなくても、「繫盛、繁盛、嗚呼商売」といいたくもなろう。昨今はインバウンド需要の増加にあやかり、訪日外国人にも人気を博しているようである。また、その再燃する人気にあやかってか、福島北部特産の干し柿「あんぽ柿」の巨大な「ガチャポン」が福島市の道の駅に登場した。
「あんぽ柿」やゼリー、羊羹が1個ずつカプセルに入った高さ1.9mの「ガチャポン」で、専用コイン(無料)を入れてハンドルを回すと、商品や引換券の入ったカプセルがランダムに出てくる。今回は「あんぽ柿」のPRで期間・数量限定だが、人気の「ガチャポン」で「嗚呼商売」となる日も近い。
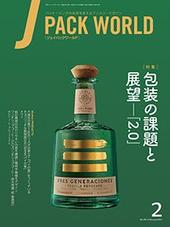
2025年2月
【特集】
- ■包装の課題と展望―「2.0」
「まだ新春はつづく」、というよりは「いよいよ新春」である。この点は月刊誌の性といえ、江崎グリコのキャラメルのキャッチコピー「ひと粒で二度おいしい」ではないが、「新春で2度楽しむ」である。
>>目次
「2.0」は「課題と展望」の第2弾というわけではなく、アフターコロナとの意を込めた第2ステージである。「再生」といった点では、継続(同質)ではあるが、違うモノ(異種)であり、むしろ「01」のように「0」を冠したかったところだが、OpenAIの最新モデルを真似たと思われそうで止めた。
こうした「維新」のような転換点を、ティッピングポイント(Tipping point)と呼ぶが、2025年はまさに「物事が特定の条件や要因に達すると、それまでの状態から急激かつ不可逆的に変化する年」となりそうである。
「蒼蠅驥尾にふして万里を渡り、碧蘿松頭にかかりて千尋を延ぶ」ように、ふるい落とされぬようしっかりと、時代に「ふし」「かかり」て万里・千尋の先まで馳せねばなるまい。
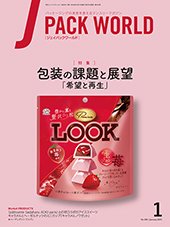
2025年1月
【特集】
- ■包装の課題と展望「希望と再生」
毎年、年頭のテーマに掲げる「課題と展望」は、いわば本誌の編集アドバイザーそれぞれのフィールドにおける定点観測である。当然、それらプロットから見えて来る未来はある。だが一方で、世界は「熱力学の第二法則」により、エントロピーの不可逆的な増大で秩序から混沌へと絶えず変化している。ただ世界はけして混沌で終わることなく、再び新たな秩序の形成が始まる。その混沌と新秩序の巨大な波のうねりに浮かぶ船舶がわれわれである。航路は見えていても、いつ波に吞み込まれるか知れない。お気楽なメディアは政権運営の難しさを喧伝するが、大小関わらず船舶の舵を握れば、希望に向けて切りつづけるしかないのだ。
>>目次
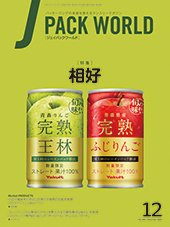
2024年12月号
【特集】
- ■相好
久しぶりの孫との再会で、「笑みがこぼれる」ことを「相好を崩す」などというが、「相好」とは仏教に由来する言葉のようである。「三十二相八十種好」との言葉を聞いたことがあるだろう。「三十二相」は仏の容姿の32の特徴で、さらに細分化したのが「八十種好」である。
>>目次
ちなみに「三十二相」には大舌相、梵声相、真青眼相、牛眼睫相、頂髻相、白毛相などがあるが、「足」の特徴が10種程度を占めている。それほどに良く歩いたということかもしれない。ある意味で、「三十二相八十種好」などの超絶した特長が、われわれに「仏」を隔絶した存在と思い込ませたのかもしれない。
研究者のなかには現実的に「『仏』は仏教僧団の総称」とする考え方もあるようだ。つまり、「三十二相八十種好」とは様々な特長をもつ僧の集まりを表わしたというものだ。確かにブッダは、「サンガ」(僧伽)と呼ばれる出家者集団で行動していた。
比肩するものではないが、包装も機能や形体、デザイン、用途など色々である。包装の「三十二相八十種好」を探すつもりはないが、多角的な視点から光を当ててみるのも面白いかと思う。
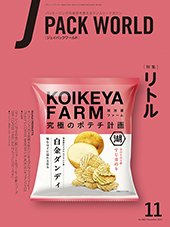
2024年11月号
【特集】
- ■リトル
マット・デイモン主演の米映画「ダウンサイズ」(2018年)を観た人はいるだろうか。人口増による環境負荷やエネルギー消費の拡大、食料問題などの解決策として、(希望する)人間を13cmくらい(縮小率93%)までダウンサイズし、世界各地に設けられた専用居住区で暮らすといったストーリーである。
>>目次
いかにも米国らしい、合理的な考えによるものだが、まったく異なる考えで「ダウンサイズ」は非常に重要なキーワードであると思う。ダウンサイズの主体は人間ではなく、その生活を支えるあらゆる機器や装置だ。また縮小率93%は極端で、一回りか二回り程度のダウンサイズでよい。
いわば「量から質へ」「マスからニッチへ」で、さらにいえば「個」をターゲットにしたダウンサイズである。最も手短に例を示せば、国内普及率90%超のスマホである。かつてOne to Oneマーケティング(日本流にいえば御用聞き)などが注目されたが、極論すれば「One to One」産業および市場の創出である。
ただ「ダウンサイズ」では映画と混同しなくもなく、「リトル」を掲げることにする。ちなみに「Little」を冠する言葉を挙げれば、「Little America」「Little Tokyo」「Little Bear」「Liittle black book」「Little Boy」「Little Dipper」「Little Dog」「Little Mermaid」「Liittle league」「Liittle Honda」などがあろうか。
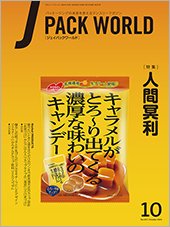
2024年10月号
【特集】
- ■人間冥利
「パッケージは物言わぬセールスマン」とは、いかにも広告代理店辺りの考えそうな詰らぬキャッチコピーである。夏季のパリ五輪は感動のうちに幕を閉じたが、「感動は最高のセールスマン」などといわれたら興醒めだ。スポーツも祭典も、なんでもかんでも「売り」に結びつけるのは無粋である。
>>目次
とはいえ、「それが仕事」といわれたらば返す言葉もない。「1+1=1」ならまだいいが、「風が吹けば桶屋が儲かる」との人工的な因果の創作では面白くない。やはり昔話の「藁しべ長者」のように、人知では読めぬ因果が面白いのだ。故人・樹木希林さんからのメッセージとした宝島社の全面広告がある。
そこには、「靴下でもシャツでも、最後は掃除道具として、最後まで使い切る。人間も、十分生きて自分を使い切ったと思えることが、人間冥利に尽きるんじゃないかしら」と希林さんの言葉が小さな文字で記されている。故意に計れる因果など創作せずとも、使い切ることでの無量の因果がある。
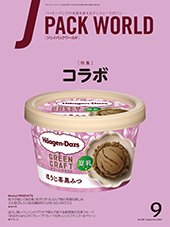
2024年9月号
【特集】
- ■コラボ
語感の良い言葉は好きである。あまり使われてはいないようだが、「COBOT」(協働ロボット)の意味も語感も好きだ。逆に嫌いのは、「FOOD LOSS」(食品ロス)、「ETHICAL CONSUMPTION」(エシカル消費)で、意味も語感も嫌いだ。理由もなくはない。
>>目次
「FOOD LOSS」は、欧州での「SAVE FOOD」のパクリだが、なぜ日本での名称は「食品ロス」。「ムダ、損失」の意味の「ロス」を、なぜ命の素である食品に当てたのか、まったく意図を解さない。また「エシカル消費」も語感も意味も悪い。まして「倫理的な消費=購買投票」などと喧伝する輩はろくでもない。
ゲーテやシラーなら「Sturm und Drang」運動を起こしているはずだ。横道にそれたが、「COBOT」はいまだ新しい言葉で、Collaborative Robotの短縮形(CO-ROBOT)である。そこで次回は、最近は国内マーケットでも非常に良く目にする「COLLABORATION」をテーマとする。
「共に働く」「協力する」の意味で、ラテン語の「COLLABORARE」に由来し、「COM」(共に)との接頭辞と「LABORARE」(働く)との組み合わさった言葉である。