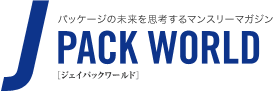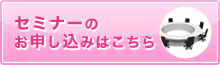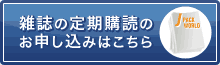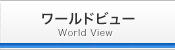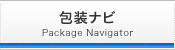トップページ > World View
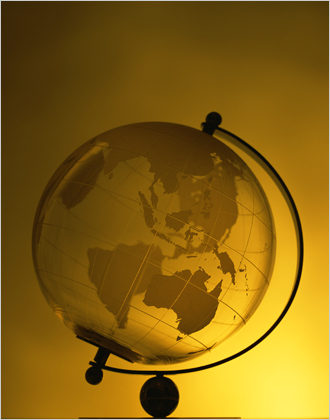
7月1日、米・カリフォルニア州北部の花火倉庫で発生した爆発火災の映像が報じられた。「独立記念日」を祝うための花火を保管した倉庫が火災し、被害は東京ドーム7個分の敷地におよび、7人が行方不明とのことである。
また7月4日、大雨でグアダルペ川が氾濫し大規模な洪水被害が発生した。流域でサマーキャンプに参加していた子どもらのうち少なくとも27人(18人は大人、9人は子ども)が死亡し、なお多くの子どもらが行方不明となっている。
これまでに約850人を避難させ、ヘリコプターやボート、ドローンを使った救助と捜索活動がつづいている。現地の予報では今後も雨は降りつづき、鉄砲水の危険もあって、地元当局は死傷者数がさらに増える恐れを警告する。
また日本では、たつき諒氏のコミック「私が見た未来 完全版」に端を発し、大災厄のXデーを7月5日とする噂や騒ぎが一部であったようだ。だが他国のこととはいえ実際、こうした大規模な災害被害の現実を目の当たりにすれば、(的中の有無はともかく)災害予知や噂が、いかに軽々で残酷なものかを痛感させられよう。
今回は、編集者の松岡正剛氏の著書「知の編集術」(講談社現代新書)から一部を紹介する。松岡氏は「スーパーやCVSが普及し、携帯電話が子どもにおよび、インターネットが広がっている今日では、いよいよ一人一人による各自の編集力が急速に要請される」と述べる。
それは、政治家らのいう「自己責任」であり、松岡氏のいう「自己編集」である。松岡氏はごみの分別にたとえて、「ごみ」の一つずつから「情報」を読み取り、誰かに任せるのではなく自分で「情報編集」するということだという。
* * *
遊びからは多くの興味深いことが見えてくる。ただし大人の遊びではなく、子どもの遊びだ。大人の遊びは戦争や不倫やギャンブルに象徴されるように、もはや遊びの本質を失っている。それに対して子どもの遊びは子どもっぽくて純粋だから興味深いのではなく、むしろ原型としての大人の遊びを残しているから興味深い。
私が世界の遊びを調べはじめたのは、いったい世界の子どもの遊びは互いに似ているのかどうかという関心をもったのがきっかけだった。結論をいえば、子どもの遊びは世界中で大変よく似た傾向をもっていた。ルールもよく似ているし、罰のとり方も似ている。
鬼になるなり方、交代の仕方もそんなに変わりはない。人数の束ね方や複雑さかげんも共通することが多い。異なる点は地域によって呼び方や名づけ方が違う点である。そういったネーミングには地域の文化の特質が如実に反映される。とりわけアジアとヨーロッパとは違っている。
遊びというものは解放のようでいて束縛であり、束縛のようでいて解放であるという特徴をもっている。その両方がなければ遊びは遊びにはなりにくい。また、一人遊びと二人遊びと集団遊びとの間には、微妙なズレがある。
このズレは子どもにとって大切なもので、たとえば二人や集団で遊んだ楽しさをいつか一人で再現したくなるときに、子どもはこのズレを意識しながら「一人演じ分け」という方法を習得する。ロールプレイの内在化が起こるのだ。
すなわち、楽しかった遊びを一人で再現しようとすると、そこには体験の「情報化」という作業が必要になる。楽しかった記憶をアタマのなかで再構築する必要があるわけだ。カラダで体験した遊びは、ここで頭のなかに移っていく。これが情報化である。そこにはズレが生きている。
ついで、この情報化された体験を自分一人の遊びに振り分ける。そこにはちょっとしたシナリオや舞台設定や役割の配分が必要になる。なにしろ複数で遊んだ体験を、自分一人の遊びに変換するのだから、色々工夫がいる。これが「編集化」なのである。
編集術は、このように遊びやゲームのような発端と終結がある情報の流れを、いくつかの場面に振り分け、組み替えることに始まっている。まず情報化、ついで編集化である。逆に、一人遊びや二人遊びの体験を集団に拡張したいときもある。
このときも決まって「情報化」と「編集化」を起こす。一人遊びの体験が情報化されて一般性をもち、それが編集化されて、さらに適応力をもつ。ここにもズレが生きてくる。そして、そこに新たな工夫が発生し、遊びはゲームとしてのシステム性をもつに至るのだ。
「ごっこ」「しりとり」「宝さがし」には、このような仕組みが真に巧く採り込まれていた。子ども遊びには、われわれが学ぶべきことが一杯詰まっている。とくに編集の方法にとって学ばされることが多い。
情報を編集するという目でみると、情報の特徴の掴み方(ごっこ、しりとり)、その情報の再生の仕方(ごっこ、宝さがし)、情報の探し方や入手の仕方(宝さがし)、その情報の連絡の仕方(ごっこ、しりとり、宝さがし)、次の情報への進み方(しりとり)、そして情報のマッピングの仕方(ごっこ、宝さがし)。
これらの遊びには、こうしたことがしっかりとビルトインされている。われわれは子ども時代からこうした遊びを通して、編集稽古をしてきたといえよう。そう考えてみると、結局、遊びとは編集そのものなのである。編集のない遊びはなく、遊びのない編集もない。そういえるのだ。
すなわち、編集術の基本は遊びから生まれてきたものだ。今は分かりやすくするため子どもの遊びだけを取り上げているが、実は大人になってからの遊びにも、ほぼ同じことが当てはまる。
もう一つ、子どもの遊びで注目すべきは、そこには初歩的なルールが発生しているということだ。どんな遊びにもちょっとしたルールがつきもので、それがなければ「じゃんけん」も「鬼ごっこ」も成立しない。遊びのルールというものは複雑すぎては成立しない。
単純すぎてもダメである。地域によって解釈が大幅に変わってしまうようでもいけない。では、どのようにルールが決まるのかというと、ちょうどコンピュータやマルチメディアの技術世界と似て、ユーザー(各地の子どもたち)が受け入れやすい度合いに応じて、いわばデファクトスタンダードで決まっていく。
こうして遊びはルールをつくっていく。ということは、編集もルールを自発させるという目的をもっているということだ。これを「編集的ルールの自発性」という。編集はルールを発見するゲームでもあったのだ。ところで、「ごっこ」「しりとり」「宝さがし」という子どもの遊びの基本三型は、私も最近になって気づいたのだが、学習の基本三型にもなっている。
「ごっこ」は模倣という学習の基礎を、「しりとり」は言葉やイメージのつながりを学ぶための基礎を、「宝さがし」はヒューリスティック(発見的)な思考やそのための準備をしていく必要性を、それぞれ学習するための基礎に当たっている。
そう考えて、編集工学研究所では1998年後半から東京大学・慶応大学・東京工科大学、メディアファクトリーの共同研究として、この3つの基本型の遊びを使った学習型ソフトウェアの研究開発に取り組んだ。「2+1」プログラムという。
3つの遊びを学習の基本型としてコンピュータシステムに入れてみたのである。テストをしてみると、なかなか子どもたちの評判がよい。それはそうだろう、これらはもともと子どもたちが長い歴史をかけて創造したマスタープログラムだったのだ。
遊びの本質は編集にある。ということは、逆に、編集の本質は遊びにあるということなのである。
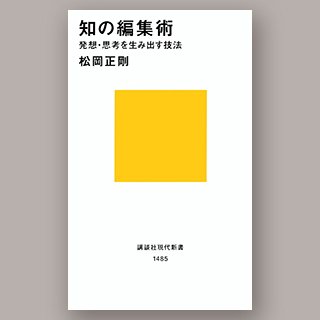
松岡正剛(まつおか まさたけ)
1944年、京都市生まれ。早稲田大学仏文科出身。東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授を経て編集工学研究所の所長、イシス編集学校の校長を歴任。1971年に友人らと工作舎を設立し、雑誌「遊」を創刊する。
1987年に編集工学研究所を設立し、日本文化、経済文化、デザイン、文字文化、生命科学など多方面の研究成果を情報文化技術に応用する「編集工学」を確立。日本文化研究の第一人者として「日本という方法」を提唱し、私塾「連塾」を中心に独自の日本論を展開。2000年にはイシス編集学校を設立、書評サイト「千夜千冊」の執筆をスタート。2024年8月に80歳で死去。