トップページ > World View
生活にパッケージの形や色彩が創造する変化

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
パリなどの欧州の都市を訪れると感じるのは、そこで暮らす人たちの特長として色を好むということである。それは衣類をはじめ身の周りのモノに表れているとともに、日本の生け花とはまた違った装飾として花を家内に飾ることである。
それは、日常に「変化」を感じるためではないかと思っている。欧州の都市は、まさに自然災害などの外環境から生活を守るために創られた巨大な城である。また四季折々の日本の気候風土とも異なることから、暮らしのなかで自然の変化というものは感じにくいのかもしれない。
もちろん日本でも近代都市では同じだが、長い歴史のなかで自然と調和し、また積極的にその変化を生活のなかに取り入れてきた感性には、あまり人工的な変化は必要なかったのかもしれない。ただ近代化のなかで、そうした感性を少しずつ失いかけているようにも感じられる。
近代看護教育の母と呼ばれるナイチンゲールは看護でも、そうした「変化」を患者に感じさせることが治癒力を高める効果があるという。逆に考えれば、自然の変化をとらえる感性を失いつつあるということは、健常者のようにみえても実は病を発症しているとはいえまいか。
かの詩人ゲーテは「人はほんとうに劣悪になると、 他人の不幸せを喜ぶこと以外に興味をもたなくなる」と言い放ったようだが、そこまで病に蝕まれてはいないと信じたい。今回は、フローレンス・ナイチンゲールの自著「看護覚書(Notes on Nursing)」(訳:湯槇ます、薄井坦子、小玉香津子、田村真、小南吉彦、現代社)から、看護での大切な「変化」に触れた言葉を紹介したい。
* * *
美しい事物、物を変化させること、とりわけ輝くように美しい色彩が病気の人に及ぼす影響については、まったく評価されていない。このような色彩や変化への渇望は、ふつうの患者の「気まぐれ」と呼ばれている。たしかに患者が気まぐれで、たとえば、全く相反する性質のものを同時に要求したりすることも多い。
しかしそういうことよりも、(いわゆる)「気まぐれ」が、その患者の回復にとって何が必要であるかを教えてくれる、きわめて貴重な指標であることのほうが、はるかに多いのである。看護婦が、患者のこの(いわゆる)「気まぐれ」について、注意深く観察するなら、それは得るところがあるであろう。
私が見てきたところでは、熱病患者の場合(私自身も、熱病で倒れたときに感じたのであるが)最もはげしい病状を表わすのは、(仮兵舎などに入れられて)窓から外がまったく見えず、見えるものは天井や壁面の板の節目ばかり、といった患者たちであった。
色鮮やかな花一束に狂喜した熱病患者たちの姿を、私は一生忘れられないであろう。そしてまた、(これは私自身の場合であったが)病床に一束の野の花が届けられたときのこと、そしてそれ以来、回復への足取りがずっと速くなってきたことを、今もありありと思い出す。
この効果は、単に気分的なものにすぎないと、人々は言う。しかし、けっしてそんなものではない。効果はまさに身体にも及ぼすものである。どういう経路で物の形状や色彩や明るさなどの影響が身体にまで及ぶのか、その作用機序はほとんど知られていない。
しかし私たちは、現実にそれらが身体的効果を持つことを知っているのである。患者の眼に映る色々な物の、その形や変化や色彩の美しさ、それはまさに、患者に回復をもたらす現実的な手段なのである。しかし、変化といっても、それは(ゆっくりした)変化でなければならない。
たとえば、患者に十枚ほどの版画を見せるとして、それを一気に矢継ぎ早に見せるとすると、患者は十人のうち九人までは、寒気がしたり目眩いがしたり発熱したり、あるいは、どうかすると吐き気を催したりさえするであろう。
しかし、同じそれを見せるにも、まずその一枚を患者の見える場所に掛け、一日おき、あるいは一週間、一ヶ月おきに取り替えるようにすれば、その変化が患者をどんなにか愉しませることになるであろう。病室にはびこる愚かと無知の極みをみごとに物語るものとして、こんな実例がある。
患者を炭酸ガスが最も多い成分かと思われるほど汚れきった空気のなかに放置しながら、その一方、切り花や鉢植えのもち込みを、健康に害を及ぼすという理由で禁止するような看護婦がいる。いったい病室や病棟が植物で「過密状態」になるほど持ち込まれることがあるであろうか。
また現に持ち込まれている植物が夜間に発生させる炭酸ガス量といっても、蠅一匹も毒しはしないであろう。それどころか植物は、混み合った部屋のなかで、室内の炭酸ガスを吸収して酸素を産出してくれるのである。切り花もまた、水を分解して酸素を出してくれる。
百合などの花は、その匂いが神経系統を衰弱させる働きがあるといわれており、それは正しいが、そうした花はその匂いでそれと簡単に判断できるので、避けることができる。心が身体に及ぼす影響については、多くの言葉が語られ、多くの書物が書かれていて、その指摘のほとんどは正しい。
しかし私は、身体が心に及ぼす影響について、もう一歩考え進んでほしいと思う。あなた方だって色々な心配ごとに悶々とすることもあろう。ところが健康人であるあなた方には、リージェント街に繰り出したり、田舎に散歩に出かけたり、場所や相手を変えて食事を愉しんだり、そのほか色々な気晴らしが、その気になれば毎日でもできる。
あなた方は気づいていないであろうが、それによって、あなた方の心の悩みはどれほど軽減されていることだろう。その一方、これもあなた方は気づいていないであろうが、そのような変化を持てない病人の場合、心の悩みはますます募り、病室の壁面にまで心配ごとが掲げられているように見える。
ベッドの周囲に心配ごとの亡霊が彷徨うのを感じ、そうして変化という救いの手が差しのべられない限り、つきまとって離れぬ想念から逃れることは不可能となっているのである。胸のなかでは、愉しい想いは抑えられ、なぜか辛い想いばかりが頭をもたげてくる。それは病人自身にとって大変な苦痛なのであるが、なぜそうなってしまうのか、自分にも分からない。
そこで病人は、その理由を考えて自問自答する。そんな自分自身を不甲斐なくも思う。しかしどう足掻いてみても、すべてはムダなのである。実際のところは、まともにその理由を詮索してみたりするよりは、書物とか会話とかに熱中できて、お腹の底から笑った方が、遙かに簡単に、この辛い苦悩から逃れられるのである。
あるいは、笑うだけの体力もない場合いもあろうが、そのときに患者に必要なものは、自然が与えてくれるあの感銘なのである。病人に生命のない壁面を凝視させておくことの残酷さについては、すでに述べた。多くの病人の場合、とりわけ熱病の回復期にあっては、病室の壁面は病人に向かって、ありとあらゆる形相を見せるのである。
ところが、それが花であれば、けっしてそういうことはない。その形や色彩は、いかなる議論や詮索にもまして、患者から苦悩をぬぐい去ってくれる。病人というものは、脚の骨折のときに他人の手を借りないかぎり脚を動かせないのと同じように、外から変化が与えられないかぎり、自分で自分の気持ちを変えることができない。
まったくのところ、これこそ病気についてまわる大きな苦悩なのである。それは、ちょうど骨折した四肢にとって一定の肢位を保っていることが最大の苦痛であると同じである。いつも不思議でならないのであるが、自ら看護婦と称する教養豊かな人々でさえ、こんなことしている。
彼女たちは、自分の生活や仕事については、一日に何度も、あれこれ変化を持たせておりながら、寝たきりの病人たちを看護しているというのに、病人の身の周りに変化をつけて気分転換を図ったりなどまるでせず、ただじっと重苦しい壁面を見つめさせておくのみである。
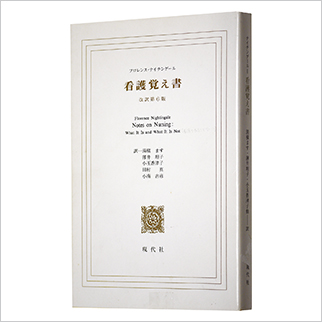
フローレンス・ナイチンゲール
1820年5月12日にトスカーナ大公国の首都フィレンツェで旅行中に生まれ、フローレンス(フィレンツェの英語読み)と名づけられる。若き日に、語学や哲学、数学、天文学、経済学、歴史、美術など様々な教養を身につける。クリミア戦争に看護婦として従軍し、ロンドンの聖トーマス病院に付属したナイチンゲール看護学校を設立。これは世界初の宗教系でない看護学校で、現在はキングス・カレッジ・ロンドンの一部となる。看護婦であり、社会起業家であり、看護教育学者。近代看護教育の母とも呼ばれる。1910年8月13日に逝去。







