トップページ > World View
一つのパッケージに表われる人間の真実

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
緊急事態宣言下で無観客開催を余儀なくされたが、57年ぶりの五輪の東京大会を格別な思いで観戦した人は少なくないに違いない。「艱難に会って初めて真の友を知る」というが、これまでの大会以上に国や地域、性別や競技種目を超えた、また選手と観客の一体感が生まれたように思う。
感染拡大に囚われて、心ない言葉をぶつける人もいるようだが、熱戦を繰り広げたアスリートたちの真摯な姿や、試合後のコメントで一様に口をつく"謝辞"に触れて、あらためて「スポーツは本当にすばらしい」と心から思うことができた。
まだパラリンピックを残しているが、アスリートはもとより、コロナ禍に耐えて開催準備と運営に献身してくださった大会関係者のすべての皆さまに心より御礼を申し上げたい。感動と感謝をありがとうございました。そんな五輪開催を前に、親しい知人から1冊の本を紹介いただいた。
ノンフィクションライターの松下茂典氏の著書「円谷幸吉 命の手紙」(文藝春秋)である。今回、ここから紹介しようとも考えたが、さすがに躊躇があった。57年前の東京大会で、マラソン3位入賞の活躍を目にした人には、すぐに察しのつくことであろう。
円谷は次のメキシコ大会開催の年に27歳の若さで、突然の自害を果している。「命の手紙」とは円谷氏の「遺書」である。知人は当時、新聞掲載された円谷の遺書を読み、心を大きく揺さぶられたようだ。五輪開催の夏に偶然にも書店でこの本と出会い、そのことをありありと思い出したようであった。
出会いとは誠に不思議であり、時空をやすやすと超えゆくものである。そこで今回は、やはり命を通じた「出会い」に導かれた、小川洋子氏の著書「アンネ・フランクの記憶」から「はじめに」の一部を紹介する。
* * *
数多く残っているアンネ・フランクの写真のなかで、私が一番気に入っているのは、夏の海辺で撮られた一枚だ。二人の少女がこちらに背を向け、並んで立っている。小さな方がアンネで、大きい方がマルゴー。撮影された年月日は分からないが、九歳と十二歳くらいだろうか。
ただはっきりとしているのは、ドイツ軍がオランダに侵入する前、フランク一家がまだ夏の休暇を海辺で楽しむことができた時代の写真であるということだ。二人は首の後ろで水着の紐を結び、下にはおそろいのチェックのショートパンツを履いている。
マルゴーの背中は丸みをおび、女性に近づいてゆくきざしがすでに漂いはじめているが、アンネの後ろ姿にはまだ十分なあどけなさが残っている。肩甲骨が浮き出し、腕も足もか細い。浜辺には影が二つ、寄り添うように写っているが、顔の表情は分からない。
マルゴーは心持ちうつむき加減で、アンネはまっすぐ頭を前に向けている。海水浴客の姿が遠くにぼんやり見える。それにしても、不思議な写真だと思う。オットー・フランクはなぜ子どもたちの後ろ姿など撮ろうと思いついたのか。
同じ頃撮影された海辺の写真では、みんなが微笑んでいる。お母さんは若くて美しく、おばあさんも元気で、子どもたちはアイスクリームを頬張っている。一点の陰りもない和やかさが伝わってくる。なのに、この写真だけは、どことなく特別な手触りをもっている。
ふと目を離したすきに、二人が海の彼方へ吸い込まれてしまうのではないかという微かな不安、その無防備な背中を抱きしめてあげたいという切ない願い、そんなものが湧き上がってくる。彼女たちは何を見ているのだろう。泳ぎ疲れてただぼんやり佇んでいるだけかも知れない。
父親の注文に応じポーズをとっているのかもしれない。けれど私には、二人の未来―あまりにも短い未来―を暗示するものが、そこに宿っている気がして仕方ない。じっと見つめていると、カメラをのぞくお父さんを置き去りにして、二人が今にも歩き出してゆきそうな錯覚に陥る。
「駄目よ。そっちへ行っちゃ駄目よ」と、私はつぶやくが、もちろん声は届かない。彼女たちは振り向きもせず、砂浜に足跡だけを残しながら遠ざかってゆく。二人の向こうには、どこまでも海が広がっている。
これからアンネ・フランクの足跡をたどる旅について書き付けてゆく間、机の隅にいつもこの写真を置いておこうと思う。彼女が残した日記の言葉たちを手がかりに、ほんのわずかでも彼女の背中に触れることができればと願っている。
アンネを語ろうとすれば、当然ナチス・ドイツや人種差別問題やホロコーストについて考えなければならないだろう。けれど、私が本当に知りたいのは、一人の人間が死ぬ、殺される、ということについてだ。歴史や国家や民族を通してではなく、一人の人間を通して真実を見たいのだ。
この写真は、拡散しようとする私の視点を、一点に引き戻す役割を果してくれるだろう。と同時に、十代の頃からずっと感じつづけてきたアンネに対する親愛の情が、今でも褪せていないことを、私に確認させてくれるだろう。
二十六歳のときに小説の新人賞をもらって以来、私は幾度も同じ質問を受けるようになった。
「どうして小説を書くようになったのですか?」
これはとても大事な質問だけれど、本気で答えようと思ったら、やはり途方にくれてしまう。語り始めたら一晩中でも足りない気もするし、いざとなると一つも言葉が浮かんで来ないような気もする。だから、その都度思いついたままを答えていた。
「子どものころ、?のお話をつくって、大人たちを驚かせるのが好きだったから」「とにかく小説を読むのが楽しくて、いつしか自分にも書けるのではないかと錯覚をいだくようになったから」「虚構の世界を書くことで、現実の自分を冷静にとらえたかったから」等など...。
しかしいつも、本質にまでは届いていない物足りなさを感じていた。やがて、私は妊娠し、子どもを産んだが、その間もずっと休むことなく小説を書いた。悪阻でものが食べられないときも、夜明けに授乳しているときも、おしめを畳んでいるときも、実生活があわただしく混乱していればいるほど、私は小説をつくり出すための時間を欲した。
自分の本を出すことが小さいころの唯一の夢だったのに、思いもかけずあれよあれよという間に叶ってしまった。何か目に見えない幸運に導かれているような気がした。そして次第に、この導きの源泉にあるものは何なのか、なぜ書くことにこれほどの救いを感じるのか、自分でも知りたくなってきた。
あらためて、じっくり考えてみて行き着いたのが、「アンネの日記」だった。私が一番最初に言葉で自分を表現したのは、日記だった。その方法を教えてくれたのが、「アンネの日記」なのだ。
学校の図書館で初めて、この本と出会ったのは中学一年のときだった。読書感想文の課題図書だったわけでも、社会科の授業の副読本だったわけでもない。はじめから、一つの純粋な文学として読んだ。もちろん、ここに記された事柄が現実だったことは分かっていた。
ただ、ナチスの犠牲になって早世したユダヤ人の少女、という一言だけですべてをまとめることができなかった。そういう歴史的事実とはまた別の場所で、私は彼女を自分自身に引き寄せ、まるで親友の心の内側に触れるような思いで全部を読み通した。
私は今まで生きて、言葉の世界で自分を救おうとしている。そのことをアンネ・フランクに感謝したい気持ちでいる。だから今回の旅の出発点は、歴史的な現場に立ちたいとか、ユダヤ人問題を考えたいとかいう、大げさな思いにあるのではない。
特別に大事な古い友人、たとえば長年文通をつづけてきた才能豊かなペンフレンドの、若すぎる死を悼み、彼女のためにただ祈ろうと願うような思いで出発するのだ。彼女が書き付けることを願いながら叶わなかった言葉たちの残像を、私の肌で感じてみたいのだ。
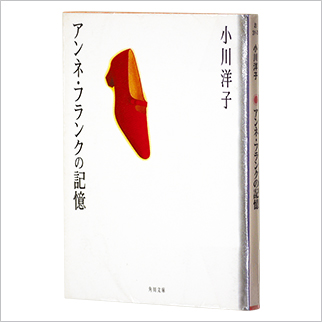
小川洋子(おがわようこ)
1962年、岡山生れ。早稲田大学第一文学部卒後、倉敷の川崎医科大学中央教員秘書室に就職。1986年9月に結婚を機に退職し、小説の執筆に取り組む。1988年、「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞を受賞。1991年、「妊娠カレンダー」で芥川賞受賞。2004年、「博士の愛した数式」で読売文学賞、本屋大賞を受賞。「ブラフマンの埋葬」で泉鏡花文学賞、2006年、「ミーナの行進」で谷崎潤一郎賞、2013年、「ことり」で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。「薬指の標本」「琥珀のまたたき」など多数の小説、エッセイがある。







