トップページ > World View
微細な変化やかすかな気配を察知する構え

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
学生のころに学んだ、「魚は淵の底に住みて浅きことを悲しみて穴を水の底に掘りて住めども、餌にばかされて鉤をのむ」との古文の一文が心に残っている。池の浅いことを憂い底に穴を掘って用心して住んでいたが、餌に騙されて釣られたとの意だが、どこか「人」を揶揄した感もある。
孔子の「九思一言」とは有名だが、たとえ聖人君主であってもそれを日々に実践することはむずかしい。つい先日も、ふいに感情を露わに失言した大臣がいたが、人もまた感情(欲望)の生きものなのである。だからといって、「九思」や危機への備え(憂い)といった不断の努力が必要ないわけではない。
ただし咄嗟のとき、その感情をコントロールできるかどうかは分からない。どちらにしても、大事なことは「覚悟」ではないだろうか。先人の残したユーモアある言葉が忘れられない。それは「どんな人でも必ず騙されるものだ。どうせ騙されるなら『この人なら』と決めて生きよ!」である。
妙ないい方とはなるが、これは"騙される覚悟"であり、"騙されてもよい覚悟"とはいえまいか。感情に動かされるのが人の性で、その不安に怯えおののくよりは"信じられる人"をみつけるべきとも解釈されよう。武道家の内田樹氏が自らの(合気道)弟子入りの体験をこんなふうに語っている。
「双方向的というより、弟子の側からの師の叡智、師の技量に対する『帰依』がないと成立しない。師の一挙手一投足、片言隻句すべてが叡智に満ち満ちていると信じている弟子からすれば、先生が何をしても、それこそくしゃみをしてもあくびをしても(中略)わが身に引きつけて無限の解釈運動を開始してしまう」と。
内田氏独特の表現ともいえようが、先人の言葉にも通じるものである。同じ"考える"ならば身から遠く「ああでもない」「こうでもない」と倦ねるより、すっきりとした方向性が見い出せよう。今回は、その内田樹氏の著書「街場の共同体論」(潮新書)から一部を紹介する。
* * *
実際に生身の本人をよく知っていて、その人の顔かたちも、性格も、趣味や家族構成も、だいたい知っているという人とは、ちょっと離れたときでも、ネットでつながっていたいというのは、それほど問題はないと思うんです。
でも、生身の人間との身体的な接触の経験がなくて、ただディスプレイ上の文字記号だけでつながっている関係となると、これはかなり脆弱なものだと思います。人間って「生もの」ですからね。一日三度ご飯を食べなければいけないし、寝なくちゃいけないし、たまには風呂にもはいらなくちゃいけない。
根詰めて働けば病気になるし、色々と不如意なものであるわけですよ。そういう身体的な制約があるのが人間なんです。でも、ネット上の人格には身体がない。そういう制約から解放された純粋知性みたいなものが、そこで発言しているわけです。
生身の人間だったら、他人に面と向かってあまり攻撃的なことや侮辱的なことは言えない。言ったらいきなり殴られるかもしれませんからね。自分に「身体がある」というのはそういうことです。殴られたら痛い。だから、言いたいことがあっても、目の前の人を怒らせるようなことは言わないで呑み込む。
身体を持っているということが、その人の社会的な行動を制約する。でも、ネット上の人格には身体がない。ネット人格は身体がないから、自由であることは確かに自由なんです。でも、それは身体を持たない自由、場合によっては固有名を示さないことで得られる自由なわけです。
ネット人格の自由というものは、固有名を持ち、家族を持ち、通っている学校や勤め先がある生身の人間の、限定性を切り捨てることで成立している。だから、この自由な人格があまり活動的になると、本体がそちらに移ってしまう。
固有名があって、家族がいて、学校に通っていて、友だちや教師からあれこれと評価されたり査定されたりしている自分の方が「自分らしい」存在様態だというふうに思い込むようになる。バーチャルの方が実で、リアルの方が虚になってしまう。
すると、リアルの方がどんどん非活動的になる。社会的には仮死状態を演じるようになる。それが「引きこもり」という病態の一つのありようだと思います。リアルな本人は、非社会的だが、ネット上では多動的という人格解離は、今あちこちで起きています。
さきにも言った通り、仕掛けというか、制度の問題なんです。今の子どもたちは、「礼儀正しく振る舞う」という枠組みを経験したことがないだけなんです。道場は礼儀が正しくなければいけないとか、清潔に保たなければいけないという決まりなんです。
そう作り込んであるから、子どもたちもすぐにルールは呑み込みますよ。礼もするし、敬語も使うようになる。礼節を重んじるためにわざわざ武道を迂回するというのは、僕はおかしいと思います。武道が礼節を重んじるのは、それなりの理由があるわけです。
それは端的に言うと「身体に対する敬意」、あるいは「身体を通じて発動する巨大な力に対する敬意」です。自分の身体、相手をしてくれる人の身体、それぞれについて丁寧に観察し、感触を味わい、微細な変化を感知することができないと、武道の稽古は成り立ちません。
身体の感度が敏感になるように、道場というシステムは合理的に設計されています。だから、みんな道着を着用して、道場の出入りでは正面に礼をし、稽古の相手にも必ず礼をする。それは人格的なものに対する敬意という以上に、そこに顕現してくる巨大な力に対する、一種宗教的な畏敬の思いの表れなんです。
武道というのは、人間をはるかに超える自然力、「野生の力」が人間の身体を通じて発現するのをどうやって制御するか、そのための技法の体系です。自分の筋力や心肺機能を高めることだけが目的じゃない。
もちろん、そういう基礎的な身体機能を高めておかないと、巨大な「野生の力」が自分の身体を通過して発動するという経験ができないから、身体をつくる必要はあります。でも、それは「導管」みたいなものなんです。そこをすさまじい量の激流が通過できるようにするためには、パイプの径を大きくし、パイプの鋼鈑を厚くしておかないといけない。
だからそうする。パイプの径が大きいとか、鋼鈑が厚いということそれ自体が稽古の目的じゃないんです。「そこを通過するもの」に対する備えなんです。ですから、道場で子どもたちが礼をしている相手は先生じゃないんです。先生を通じて「巨大な自然力」「野生の力」に対して礼をしている。
野球でプレーボールのとき、ピッチャーがボールに対して帽子をとって一礼しますよね。あれは別に審判やキャッチャーに向かって礼をしているわけじゃない。ボールに対して礼をしているんです。ボールが象徴している「野球の神さま」に対して礼をしている。
素の状態で道場に入ってはいけない。いったんそれまでの自分をリセットする。そして、身体感度を上げて、感覚を研ぎ澄ます。身体感度を上げる。そうしておかないと、自分の身体で起きた微細な変化が感知できませんから。かすかな気配を察知しようとするとき、人間は黙るでしょう。
身体の力みをとって、耳を澄まして、表情も消えますよね。それが「礼」なんです。初詣のときに、神社仏閣の前で手を合わせるときに、みんな頭を垂れて、黙りますでしょう。大声でおしゃべりしたり、耳にヘッドセットつけたままお祈りしたり、手足を振り回して参拝する人なんか見たことないでしょう。
神殿や本尊に向かって合掌しているとき、人は耳を澄ましているんです。「家内安全」とか「五穀豊穣」とか「学業成就」とか祈りながら、みんな神さまからの「返事」を待っているんです。何か聞こえるんじゃないかなと思って。
これまで何十年も神仏を拝んできて、神さま仏さまから「ご返事」があったことなんか一度もないのに、つい耳を澄ませてしまう。それが「礼」の基本姿勢なんです。人間たちの住む世界とは別の世界からのシグナルを聴き取ろうとする構えのことです。だから、「礼」と「祈り」は身体のかたちが似ているんです。
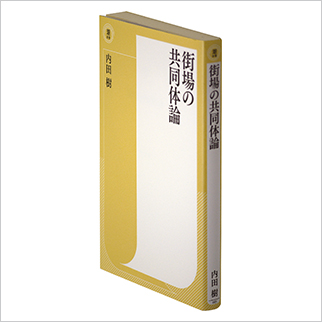
内田 樹(うちだ たつる)
1950年東京都生まれ。東京大学文学部仏文科卒。東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程修了。学院大学文学部総合文化学科教授。専門はフランス現代思想。神戸女日本の哲学研究者、コラムニスト、思想家、倫理学者、武道家、翻訳家、神戸女学院大学名誉教授。京都精華大学人文学部客員教授。合気道凱風館館長。







