トップページ > World View
心の原風景に深くかかわる発想や表現法

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
ニッカウヰスキー創業者・竹鶴政孝と妻のリタの生涯を題材としたTV小説「マッサン」が幕を閉じた。その中でエリー(リタ)が、マッサンへの最後の手紙に認めた「Life is an adventure」との言葉が非常に印象的であった。とくにアドベンチャーとの言葉は不思議ななつかしさを感じさせる。
本来、誰人も自らの未来を推し量ることはできない。それだけに「Life is an adventure」とのことを、われわれは忘れていたのかもしれない。映画「風と共に去りぬ」の(スカーレット・オハラの)のセリフではないが、「Tomorrow is another day」で「明日は明日の風が吹く」のである。
それだけに「今を深く生きる」ことが大事ではなかろうか。ときに追われて、様々な出来事や経験をただ、あわただしく過してゆくのではなく、ときに深く記憶の奥に分け入って掘り下げてみることも必要である。「過去というものは現在の中にしかない」とのごとく、未来もまた現在の中にしかないのだから。
「一人で内面を探索するのもいいけれど、表現方法の違う人と刺激し合いながらやってみるのも、意外な発見や展開があっておもしろい」とノンフィクション作家の柳田邦男氏はいう。
そこで今回は、その柳田邦男氏と絵本作家の伊勢英子氏とのデュオエッセイ「はじまりの記憶」(講談社)からプロローグとなる対談の一部を紹介したい。「それは後ろ向きに昔を回顧するだけじゃない。今の自分の存在理由を確認する作業なんですね。僕も表現活動の転機を迎えているので、これはすごくアドベンチャラスな『旅』になりそうな予感がします」と柳田氏はいう。
◇ ◇ ◇
(柳田)人間のいちばん大事なものは、自分の心の奥底に拭い去ることのできないものとして刻まれた人生の節目節目の情景なんですね。人とのかかわりの、ある瞬間とかある出来事とか、色々な体験の中の重要なシーンが、その人の人格形成、性格形成、さらに発想法や感情の持ち方というものにとても深くかかわると同時に、何かのときにふと顔をのぞかせる。
(伊勢)そういう風景みたいなところから大人になっていまに至るまで、何をずっと引きずって、何を捨ててきてしまったか。私、自己分析ってあまり好きじゃないのですが、ずっとそれを考えていたような気がするんです。
「風の又三郎」も「よだかの星」も「水仙月の四日」も、賢治作品の絵画化は、私の生き方と無縁ではないところで描いてきましたが、それは感じ方の原型を探しながら描いてきた、ということなのかもしれません。
(柳田)連載の挿絵を引き受けてくださることが決まったとき、担当者が伊勢さんの作品を十冊以上かき集めてくれたんです。それで、伊勢さんの自分探しの手記「カザルスへの旅」を読んだら、あっ、この人は「風の又三郎」で感じた通りの原風景をしっかりと持っている方なんだと感じた。
子どものころの風景などというものは大抵、都会で大人になるにつれて忘れてしまうものだけれども、この絵を描いた人はいつも鮮明にそれを意識して生きているめずらしい人だなと感じたんです。それから「よだかの星」の絵では、独特の深い紺や赤の色彩から人間の深淵を見据えるような重みが伝わってくる。
天にも地にも生きられなかったよだかの世界を表現しようとする画家の心眼がある。伊勢さんの絵は、そうした心の原風景と芸術的感性の重なり合いで成り立っているというか。
(伊勢)新聞の連載が終わってまもなく柳田さんが、「よだかの星」のラストシーンの絵を、「犠牲(サクリファイス)」の装幀に使いたいとおっしゃいました。
(柳田)絶対的孤立のなかで「生と死」、そしていのちの「再生」をとらえた「よだかの星」の絵のすごさが強く焼き付いていたので、それを息子の人生のメタファーとして使わせてもらいたいと思ったのです。
(伊勢)よだかは疎外感のゆえに星になったのではなく、精神の高さゆえに自らの身を燃やして星になったんだと思います。私の中の明るい空気みたいなものと、暗いといっていいかどうかわからないけれども別の面を絵の中に読みとっていただけたような気がして、すごくうれしかった。
(柳田)人間というものは誰でも、明るい面と暗い面、冷たい面とやさしい面、剛毅な面とソフトな面、あるいは非常におとなっぽい面と子どもぽい面と、様々な要素を同時に持っていると思うんです。ただ人によって、たまたまどちらかが相対的に強く出るから、それで人間のイメージが形成されてしまい、一つの枠にはめられて見られがちなんですね。
ちょうど今、講談社から全十巻という壮大な「ベートーヴェン全集」が刊行中ですが、その第一巻に添えるエッセイを頼まれて、私はベートーヴェンにおけるそういう二面性の問題を詳しく書いたんです。
ベートーヴェンといえば、「運命」「英雄」「悲愴」「熱情」といった曲から、重厚、壮大、激烈、思索的、沈鬱などのイメージで固定的にとらえがちですが、それではあまりに一面的過ぎる。
最近、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の安永徹さんと夫人のピアニスト・市野あゆみさんが普段ほとんど演奏されないヴァイオリン・ソナタの第六番と第十番を演奏したのを聴いて、すごく感動すると同時に、ハッと気づかされたんです。
第六番はまるで十代の感性のような繊細な美しさに満ちているし、第十番は若い恋人同士の甘いささやき合いそのものなんですね。ヴァイオリンがひと言語りかけると、ピアノが包むように答え、またヴァイオリンが歌う。
(伊勢)ベートーヴェンの何歳ごろですか。
(柳田)42歳になる直前です。実らぬ恋を重ねてきた彼が、おそらく情熱を燃やした最後の相手とみられる女性に対して、出すことのなかった「不滅の恋人への手紙」を書いた直後あたりなんです。それであらためて気づいたんですが、あの可憐な小品「エリーゼのために」も40歳ごろの作品なんです。
失恋を繰り返し失意つづきの40代のごつい男が、一方でこういうやわらかく優しい曲を作っている。ベートーヴェンだって、優しさ、あたたかさ、傷つきやすさ、切なさ、といった繊細な側面を多分に持っていたわけです。人間の心の中は多面体だし、奥ゆきは深いですね。
人間を見るには、よほどこちらがやわらかくならないとその実像をとらえられない。
(伊勢)自分のことを含めて、人間が持っている全体像を知るのは大変なことですね。表現手段をもっていてもそうなんだから。
(柳田)表現しようとするから見えるといってもいいと思うんです。ふつうは、作家や絵描きは人よりよく見えているから表現しようとすると、逆なんですね。表現しようという衝動に突き動かされて表現しようとすると、しっかりと対象を見ていない、ディテールを見ていないことに気づく。
そこで詳しく調べたり、観察し直したり、歩き回ったりして、はじめて対象の核心や全容をつかみ、ようやく表現に入るわけです。詩歌や文章を書こうとするから、人間の心が見えてくる。絵も同じだと思うんです。自分の原風景だって、何かの形で表現しようとすると緊迫感がないと見えてこない。
(伊勢)私は子どものころからチェロを弾いていて、もちろん今は生業は絵を描くことなのですが、自分が何者であるかを探すために、十何年か前にチェリストのパブロ・カザルスのこだわりの地カタロニアまで旅にでたことがあるんです。
リュック一つで、たったひとりきりで。でも、カザルスの亡命地のピレネー山中の本当の寒村、人口何百という村にたどり着いたときに、もちろん初めて行った土地なのに、あれっ、この風景、私は知っている、この平和な光はどこかで見たことがある、すごい昔に体で感じたことがあると思った。
私はそのとき34歳だったのですが、そのときは、前へ前へ進むことで自分を探そうとしていた。絵を描く意味、家族とは何か、自分の魂は何を求めているのかって―どうやったら自分らしく生きられるんだろうと考えながら、カタロニアで出会った風景や光をたぐっていったら、34歳の日常を通り越してしまってどんどん過去へ歩いていってしまった。気がついたら、最初の記憶の場所、函館の5歳の時代に行きついていたんです。
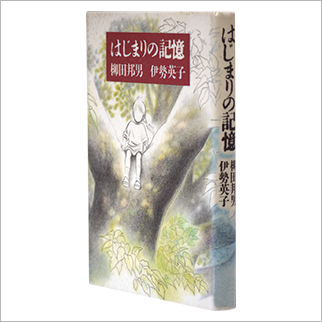
◎柳田邦男(やなぎだくにお)
1936年6月生まれ、ノンフィクション作家、評論家。航空機事故、医療事故、災害、戦争などのドキュメントや評論を数多く執筆。また伊勢英子は1949年5月生まれ、日本の絵本作家。柳田邦男の妻。







