トップページ > World View
生死を呑み込む開かれた人間観・自然観

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
「君たちはどう生きるか」とのタイトルの本をご存知だろうか。児童文学者の吉野源三郎が著した、想像上での中学生とその叔父さんとの対話集(交換手記)である。いうまでもなく論文や評論は一方通行であり、対話は双方向である。
ゆえに対話の選択には、互いの共通する問題の本質に迫り、それを解決しようとする真剣さが感じられる。対話について「両者の立場の違いや問題の所在を直視しながら、互いの間に横たわる障害を1つ1つ忍耐強く取り除いていく、人間精神の究極の建設作業である」との考えを示す人もいる。
本誌にも、長年にわたり対話をつづけてきた友がいるが、あるとき「もう、こんな話ができるのはお前しかいない」と言われたことは忘れられない。「こんな話」とは特定の何かではなく、「君たちはどう生きるか」とのタイトルに連なるものである。
誌面に止まらず、主催するセミナーや海外視察などでも、常にこの一点は逃さないようにしている。今回は、現代版「君たちはどう生きるか」を思考した姜尚中氏の著書「心」(集英社)を紹介したい。主人公の西山直広くんと先生(姜尚中)とのメールを通じた対話集である。
最後に直広くんと友人たちで創作劇を催すのだが、紹介するのはそのクライマックスでの直広くんの独白の一部である。
* * *
僕は三か月間、被災地で遺体引き上げのボランティアをしました。いろんなことを知りました。いままで考えたこともなかったことを考えました。じつのところを言うと、もともとこのお手伝いを始めたのは、震災の犠牲者を悼むとか、原子力の問題を考えるとか、そんなとがった意識からじゃなかったんです。
震災とは関係ありません。震災の少し前に病気で死んだのです。僕は彼の死をどう受け止めていいかわからなくて、頭がおかしくなりそうでした。そこに地震が起こりました。親友と同じく、何も悪いことをしていないのに、何の罪もないのに、突然命を奪われる人が何万人も現われました。
そこで僕は、教えてもらおうと思ったのです。親友の死とちゃんと向き合うために、地震で死んだ何万もの人びとに、教えてもらおうと思ったのです。人が死ぬってどういうことなのか、人はどうせ死ぬのに何のために生まれてくるのか、人が生きるってどういうことなのか、人の人生って何なのか、教えてもらおうと思ったのです。
そのために、ボランティアを始めたのです。僕はもともと水泳が得意でライフ・セーバーの資格を持ってるってだけの、恐がりの、甘ったれなんです。ですから、ボランティア、とてもこたえました。何か月も水中に放置されていた遺体ですから、ぶよぶよになっています。皮膚も崩れています。
臓器も目玉もなくなってました。いまでも思い出すとめまいがします。寝られない日もあります。しかも、そんな思いまでして引き上げても、よろこばれないことがあるのです。なぜ引き上げたのだ、見つけてくれない方がよかったって。意外でした。僕はますます自分の疑問に対する答えを見失いました。
そんなとき、僕がお世話になっているある先生が教えてくれたんです。僕のやることは、「ライフ・セービング」じゃなくて「デス・セービング」だって。命を救い上げているのではなくて、死を拾い上げているのだと。
ライフ・セービングというのは、人の尊い命を助けますが、デス・セービングはそうではありません。見つからない方がよかったと言った方があったように、むしろ「生きているかもしれない」という希望を無情に断つものですらあります。
では、デス・セービングは無意味かっていうと、そんなことはないんです。死は生と隣り合わせにあるんです。死は生につながっているんです。だから、死はそもそも生の中にくるみ込まれているんです。僕たちはこの明るい社会の中で「生」の側面ばかり見て、「死」は切り捨てちゃってます。
けがらわしいものだとばかりに、見えないところに遠ざけてます。でもそれは間違いで、本来、生と死は半々であるはずなんです。だから、僕の先生は、死にちゃんと向き合えば生の意味も見えてくる、生きることの意味が生き生きと際立ってくるはずだっておっしゃいました。
「君はいま、それができる場に立っている。それは見知らぬ人の理由もわからぬ死ではあるけれども、その一つひとつをちゃんと受け止めてごらん。そうすれば、君の探し求めていることの答えもきっとわかるはずだ」とおっしゃいました。
僕は、なるほどそうかもしれないと思って、苦しかったけど頑張って続けたんです。「人の死ってどういうことなのか。生ってどういうことなのか。あるいは人間って何なのか」。正直いって、いまでもハッキリ理解できたわけではありません。
でも、強く実感できたことがあって、それは、亡くなった方に接するほど、生きることの大事さ、自分が生きていることの尊さ、ありがたさが身にしみて感じられてくるんです。生きててよかった、せっかく命があるんだからちゃんと生きなくちゃいけない、生を無駄にしちゃいけないという気持ちが湧き起こってくるんです。
前はちょっとつらいことがあったら、ああ、死んじゃいたいなんて思いましたけど、いまは思いません。僕は生きている、なんてうれしいことだろう、なんて素晴らしいことだろうって思います。これはきっと亡くなった方から力をもらっているのです。
生と死がつながっているとはそういうことだと思います。それがわかったときから、自分でやっていることは、亡くなった方から思いをもらって、生きる力に生かすことなんだと思うようになりました。そして、それは僕だけのためではなく、亡くなった方のためでもあるとわかりました。
僕が「生きる力」をもらえば、その方の「死」も輝く。その方の死が輝くような「永遠」になるのだって。-----って、僕の話しばかりしちゃいましたけど、この劇の夫婦の死の意味も、そんなところにあるのです。彼らは間違っていたかもしれない。自然に逆らっていたかもしれない。
でも、僕らが、彼らの死に接していちばんやらなきゃならないことは、彼らの誤りを追求することではなく、彼らを葬り去ることでもなく、単純に彼らと反対の方向に舵を切ることでもなく、むしろ、間違いも含めた彼らの人生をちゃんと受け止めて、僕らの中にそれを抱いて生きることじゃないかと思うんです。
生きることと死ぬことって、たぶん白か黒かの選択じゃないんです。僕の先生が言ったように、死は生の中に、生は死の中にお互い含まれあっているんです。ですから、劇の中で出てくる「自然」というのは、自然と人工の両極端の対比のことをいっているんじゃない。
「間違い」というのは、正解か間違いかという両極端の対比じゃないのです。〇か×かではないのです。けがれた黒を含むことで、白が際立って輝く。自然の中に、すでに不自然が含まれているんです。間違いも含んでいるからこそ、正しいことをだいじにしたくなるんです。
そういうこではないでしょうか。だから、だいじなことは、もしかしたら自分は間違っているのかもしれない、だとしたらどこで間違ったんだろうという疑問を常に胸に抱きながら生きていく、それではないかと思いました。これがライフ・セービングという名のデス・セービングをすることによって、僕がお粗末な頭で悟ったことです。
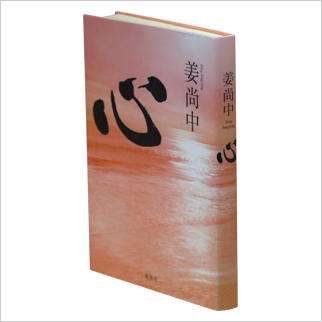
姜尚中(かんさんじゅん)…1950年8月熊本県熊本市に生まれる。在日韓国人2世。政治学者であり、聖学院大学学長(第6代)、東京大学名誉教授などを務める。







