トップページ > World View
自らの視座に拠点を置いて歴史に学べ

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
広島は8月6日、72回目の"原爆の日を迎えた。平和記念公園では「原爆死没者慰霊式・平和記念式」(平和記念式典)が行われ、松井一実市長は「平和宣言」の冒頭で「72年前の今日、8月6日8時15分、広島の空に『絶対悪』が放たれ、立ち昇ったきのこ雲の下で何が起こったかを思い浮かべてみませんか」と呼びかけられた。
そして「今年7月、国連では核保有国や核の傘の下にある国々を除く122か国の賛同を得て『核兵器禁止条約』を採択し、核兵器廃絶に向かう明確な決意が示されました。こうしたなか各国政府は、『核兵器のない世界』に向けた取り組みを更に前進させなければなりません」と訴えられた。
イギリスの歴史家・トインビー氏が文明の興亡の歴史から論じた「挑戦と応戦」とは有名だが、変革の作用にはそのスケールに応じて反作用が必ず表われるものである。松井氏の言葉には、「核兵器禁止条約」の国連採択への反作用に応戦する意志が表われている。
過去の歴史を否定しても取り消すことはできない。「8月6日」にも応分の反作用があり、それが「絶対悪」への応戦の力である。ゆえに変革のときこそ、真摯に歴史をみつめて学ぶことである。それが未来へ進化しつづける人類の英知であろう。
今回は、作家の童門冬二氏の著書「内村鑑三の『代表的日本人』」(PHP)から、作家の道を歩むに至った敗戦直後の"原体験"のつづられた一部を紹介したい。それが善きことであれ、また悪しきことであっても原体験をもつ人は強い。また他の人の原体験に触れ、そこに学ぶことは体験することでもある。
* * *
人生における人間と人間の衝撃的な出会いを"一期一会"という。しかし一期一会は人間に対してだけでなく、ほかの物に対してもある。たとえば本だ。わたしにとって内村鑑三さんの書いた「代表的日本人」との出会いは、まさに「敗戦直後における一期一会の出会い」だった。
昭和20年(1945年)の敗戦時、わたしは青森県の三沢海軍航空隊にいた。すでに特攻隊(特別攻撃隊)の基地になっていた。茨城県の土浦海軍航空隊で、甲種予科練(海軍飛行予科練習生)としての訓練を終えたわたしは特攻に編入され、この年の9月早々に硫黄島に出撃することになっていた。
硫黄島を基地とするアメリカのB29の日本本土空襲がすさまじく、これをなんとかして食い止めようという作戦が立てられたからである。このときは、「日本中にある飛行機を陸海を問わず全部集めて、硫黄島に殴り込む」という壮絶な作戦が立てられていた。
しかし三沢航空隊にいたときはこんなことは知らされず、あとで教えられた。このときわたしは17歳である。画家の山下清さんに「ヘイタイの位でいえば、ナ、ナニカナ?」と階級を聞かれれば、海軍飛行兵長だ。
当時、わたしが本という本を片っ端から濫読したなかに、ドイツの作家が書いた少年死刑囚を扱った小説があった。無実の罪で死刑の判決を受けた少年が死刑囚として刑務所に入れられる。かれはやがて無罪放免の望みを捨てて潔く死のうと覚悟する。
このときの少年の死の恐怖との戦いがすさまじく描かれていた。小説は、ある日突然この少年が無罪と判明して、刑務所から出され、混乱しながら社会復帰するところで終わる。後味の悪い小説だった。読後、(こんなことはいくらも例があるのかもしれない)と思った。
特攻隊は少年死刑囚ではない。しかし、死の恐怖と戦う意味においては同じだ。わたしも従容として死ぬために、襲い来る死の恐怖と必死になって戦った。わたしの場合には、まるで宇宙のブラックホールへ吸い込まれるように、体がクルクルと回転しながら、真っ暗な闇に向かって吸い込まれていく。
これがつまり死への恐怖だなと思った。そこでこの克服に立ち向かった。やがてこのクルクルは収まった。そして訪れたのは心の平安だった。わたしは、「これで従容として突入できる」という境地にまでは達した。
それまでに聞いた話では、特攻隊員の多くが、「天皇陛下万歳」とか、「お母さん」とかの最後のことばを残して突入していった。みんな恰好いい。しかしその恰好よさは、ほんとうに死への恐怖を克服した後の出来事なのか、それともまだ死というものと戦いながら突入していったのか、定かではない。
当時の三沢航空隊には、飛行機がほとんどなかった。また、アメリカ空軍の攻撃で滑走路はメチャクチャに裂かれ、さらに引きつづき攻撃を受けていた。そして8月15日、日本は敗れた。わたしたちは残務整理のために9月初旬までここにいたが、やがてそれぞれ故郷へ戻ることになった。
わたしの故郷は東京だ。無蓋車のような列車に乗って、東京駅に着いた。東京駅も焼かれ、プラットホームの台だけが残っていた。多くの被災者が溢れていた。これはテレビ(NHK、BS放送)でも「ぼくの8月15日」という題で話したことだが、わたしの胸の冷蔵庫に、どうしても消えない"原風景"がある。
わたしの戦後の生き方を決定的にした"原体験"だ。いまも凍結されたまま、じっと胸のなかの一角を占めている。東京駅に群がる被災者のなかから、わたしをじっと見つめる視線を感じた。振り向くと汚れた若い母親が赤ん坊を背負って、わたしを睨み付けていた。
脇に大きな荷物が置いてあった。焼け出されたのだろう。故郷へ向かう列車を待っていたのだろうか。わたしはその若い母親の鋭い視線に射すくめられた。いままであまり経験したことのない視線だったからである。若い母親の視線は明らかにわたしを憎んでいる。
こういう視線にいままで遭ったことはない。変な話だが、予科練は日本の人気者だった。"七つボタンは桜のイカリ"というのが謳い文句で、かなり世のなかからもてはやされた。試験も結構むずかしかった。
しかしわたしにすれば、「予科練は、海軍兵学校にいけなかった連中の吹き溜まりでもある」という気持ちがあった。わたし自身そうだった。海軍兵学校の受験資格が調っていないことと、同時に、「まごまごしていると戦争が終わってしまう」という不安感もあった。
そこで予科練へ飛び込んだのだ。旧制中学3年になったばかりのころだ。しかし、その若い母親のわたしを睨む視線の底には、「子どもだって絶対に許さないよ」という色があった。わたしがこういう視線に遭ったことがないというのは、予科練というのは社会の人気者で、みんなが愛してくれたからだ。
わたしたちよりあとの世代は憧れの目で見てくれた。悪意に接したことがなかった。それが東京駅頭でいきなり憎悪そのものの視線を叩きつけられたから、わたしはとまどった。おそらく若い母親が言いたいのは----。
「戦争のおかげで、あたしは亭主を失った。小さな子どもを残され、家も財産もない。これからどうして生きていけばいいのさ?」「あんたたちは子どものくせに、自分から進んで戦争に参加したじゃないか。しかも負けてしまった。いま、復員といってたくさんの缶詰や衣類をもらって家に戻る。それであんたたちは平気なのかい?」
「ほかの人だったら、子どもが戦争にいったのは世のなかが悪かったからだ、というかもしれない。でもあたしはそうは思わない。あんたたちは自分から進んで志願して兵隊になったのだ。あたしがいまこんな目に遭っているのも、けしてあんたたちに責任がないとは言わせないよ」
目はそう語っていた。わたしは東京駅頭で立ちすくんだ。その若い母親の視線の底にある憎悪の念にいたたまれなかったからである。わたしは若い母親から目をそらし、うなだれた。思わず(すみません)と声に出さずに謝った。これがある意味でわたしに、「原罪意識」を植えつけた。
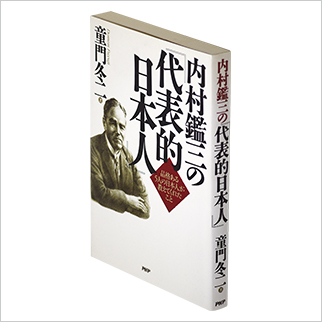
童門冬二(どうもんふゆじ)
1927年10月、東京生まれ。東海大学附属旧制中学卒業。海軍少年飛行兵の特攻隊に入隊。東京都に入都、広報室課長、企画関係部長、知事秘書、広報室長、企画調整局長、政策室長を歴任した後、1979年に退職。作家活動に専念する。小説家。1960年には「暗い川が手を叩く」で第43回芥川賞候補となる。







