トップページ > World View
パッケージ研究は人間が対象ゆえに興味や関心は尽きない

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
AIなどの研究に従事される方と話をしてみると、なぜか共通して感じられることがある。それは、AI研究の名で対象としているのは「人間そのもの」ということだ。誰しも人間であれば、その(己の)存在に興味や関心を抱くことは当然のことであろう。
ただ研究対象としてあらためて知れば知るほどに、そこにはAIなどでは到底置き換えられない奥深さがある。かつて米ロサンゼルスで訪ねたある集いで、現地のおばさんに「自身に潜在する可能性を自分で決めてはもったいない」といわれたことがある。
確かにAI研究などを通じ語られる、人間の潜在的な可能性には計り知れないものがある。ならば、人間であれば誰にも「計り知れない可能性がある」ことになろう。それを未熟さゆえであろうか、自らの限られた知見で易々と推し量り小さく纏まってしまうのは「もったいない」ということであろう。
むしろ、その未熟さが伸びしろで、計り知れない可能性の潜在するところである。そして可能性を引き出すには、母鳥と雛との「啐啄之機」が必要である。「啐」は雛が孵化しようと殻の内側からつつく音で、「啄」は母鳥が外側から殻をつつく音で、両方からつつくことで殻が割れるという意味である。
つまり自らの潜在する可能性を引き出すには、外からの働き掛けと自らの意志との両方が必要であるとのことだ。「日本の霊長類研究の創始者」と呼ばれる今西錦司氏は、その関係を「二にして一のもの」と表するが、今回は彼の代表的な著書「進化とはなにか」(講談社学術文庫)から一部を紹介したい。
* * *
種社会といえども、実際は非常にゆっくりであっても、種の枠組みというものを変えつつ進化してきたものだ、と考えられないだろうか。ここのところを表現するため、私はよく種社会とそれを構成するところの種の個体とは、二にして一のものであるという表現を用いる。
二にして一のものであるということは、どちらか一方が変わるときがきたら他方もまた変わるということである。これをもってミクロにみれば、種の個体が変わるときには遺伝子の構成の上でも、やはりそれに応じた変化があってもしかるべきであろう。
そうなるとまた種の個体とその遺伝子とは、二にして一のものであるといわねばならなくなる。少なくとも、今まで信じられてきたように遺伝子が先に変わり、その結果として突然変異を生じ、さらにその結果として種が変わるといったような一連の因果関係によって、生物の種が進化してきたものではない。
それを、そのようにしか考えられなかったというのは、誰も彼もが還元主義の落とし穴に落ち込んでいたからである。変わるべきときがきたら、種社会も種の個体も、またその個体のなかにしまい込まれた遺伝子物質も、みな同じうして変わるのでなければ、システムが壊れてしまう。
私が引用する例は、人類の進化ばかりで恐縮であるが、先にも述べた通り、オーストラロピテカスの頭蓋容量にして600ccぐらいの頭が、われわれサピエンスの1400ccぐらいの頭にまで変化するのに、200万年あるいはそれ以上もかかっているのだが、この変化は一方的に頭が大きくなる方向に向かって変化しつづけてきたとしか考えようがない。
またこれは、それぞれの時点における種の枠組みに違いはあったにしても、どの個体が死んでどの個体が生き残り子孫を残そうとも、やはりここまで進化してきたものであって、頭蓋骨容量に少しぐらいの個体差があったところで、セクショニズムで考えるように、この差がものをいって頭の大きなものが生き残ったせいだとは、到底考えることができないのである。
頭の大きいものが知能的にも優れていたのだ、というふうに考えられがちであるけれども、われわれの間だって、頭の大きさと知能の優れた方とは、必ずしも一致したものではないのである。ただそうなると、種の枠組みというものは、それぞれの時点で変わるとしても、その枠組みの変わる方向は、なんだかはじめから決まっていたように思われてくるものである。
それはつまり、種社会と個と二にして一のものであるかぎり、すでにそれぞれの個体にまでその方向性が与えられていたという考えに、われわれを導いてゆくのある。そういうところをとっても、種の個体には甲乙がないということになると、こうした種の個体によって構成された種社会というものは、これを個体の立場からみたら、一種の運命共同体にほかならない、といえないこともないであろう。
私は、先にダーウィンは進化を導く「見えざる手」を、彼のいうように自然淘汰の自然に与えて、生物が自発的、自主的に進化に携わることを拒否したといっておいたが、こうなると反対に進化のカギは、はじめから生物の側で握っていた、といえないこともないであろう。
ダーウィンの「見えざる手」は彼のセオリーとともに、一応進化の舞台からその姿を消し去ったことになろうとも、私はこれに取って代わる「見えざる手」とぶち当たるところまで、もう少し種の起源あるいは進化の起源を、追いつづけることとしたい。
人類の進化史はいまのところ、正確にはオーストラロピテカス以前にはさかのぼれないけれども、もちろんもっとさかのぼれるはずであって、それは将来の楽しみにしておくとしても、理論的にいえることは、いつかどこかである種のサルが人類に進化したということである。
まだサルの行動をしているものは、人類とはいえないし、人類の行動をとるようになったものは、もはやサルではないのであるが、ではその決め手となるのは何かというと、人類は直立二足歩行するということである。では、どのようにして人類は直立二足歩行するようになったのであろうか。
今までに色々な説が出されたけれども、そしてそれらの説では大人がまず直立二足歩行を始めたということになっているのだけれども、私はまず直立二足歩行に踏み切ったのは、大人ではなく赤ん坊であったと考えている。
どうしてこういう考えになったかというと、サルの赤ん坊に比べて、人間の赤ん坊があまりにも未発達の状態で生まれてくることが、気になり出したからである。
サルの赤ん坊は手足の握力が十分に発達したのちに生まれてくるから、生まれたときから母親の胸にしがみつくことによって、母親が群れとともに遊動生活をつづけてゆくことの妨げとはならないが、人間の赤ん坊にはそういう芸当ができないから、このような赤ん坊の生まれた母親はどこかに隠れ家を求めて、そのなかである程度大きくなるまで赤ん坊の世話をしてやらなければならない。
すなわち、サル時代を通じての芸当であった群れの遊動生活というものの隠れ家に定着している間に、未発達で生まれた赤ん坊が発達とともに直立二足歩行を始めるようになったのである。人類の起源という重大な問題を、このように簡単に説明してしまうことには異論もあるだろうけれども、順序としてはまず人類の発生上に胎児化という現象がおこって、未発達の赤ん坊が生まれるようになった。
ところが次にはこの未発達さが幸いして、赤ん坊の直立二足歩行を可能にした。あとは、この直立二足歩行に付随した現象として、たとえばすでに度々引き合いに出したように、いつかは頭も大きくなる、すなわち大脳化ということもあるところまで進んでゆくのであって、ここで起源論として一番大事なところは、一旦サルから直立二足歩行という新しい人類への道を歩み出したならば、その付随現象としての大脳化などということは、要するに時間の問題で、ほっておいてもそうならざるを得ないということである。
種としての未来の枠組みは、すでにそのとき決定されたのも同然であるということである。これを種に備わった自己完結性という言葉で表してもよいかもしれない。
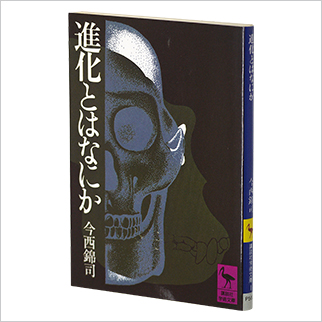
今西錦司(いまにしきんじ)
1902年1月京都府生まれ。1928年3月に京都帝国大学農学部農林生物学科卒業、1933年3月に京都帝国大学理学部講師、1939年12月に理学博士。1959年6月に京都大学人文科学研究所教授、1965年4月に日本人類学会評議員、1966年4月に日本民族学会理事、1973年6月に岐阜大学名誉教授、1974年6月に京都大学名誉教授、1978年4月に日本アフリカ学会顧問など歴任。「朝日賞」「文化功労者」「文化勲章」「従三位勲一等瑞宝章」など受賞。生態学者、文化人類学者、登山家。1992年6月に逝去。







