トップページ > World View
何もかも取り去ったあとに残る包装共通の性質とは

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
「ぼくが今日あるのは、けして自分の力や才覚のためではない、父の願いや思いというものが、ぼくの身体に伝わってきていたためではないか、という気がする」とは、パナソニックを創業した実業家の松下幸之助氏の残した言葉である。
「親孝行したいときには親はなし」とのことわざもあるが、裏を返せば失ってからはじめて親の存在、ありがたみを知るということであろう。幸之助氏も「親が亡くなってのちに、折にふれてその偉大な愛に胸を打たれる」といったようだが、「経営の神様」と呼ばれた松下氏にして然りである。
「一切合切凡庸な/あなたじゃ分からないかもね」といった歌詞のように、ましてや凡庸なわれわれは結局のところ、失ってみなければ分からないものかもしれない。それは親に限るまい。本当に大切なものほど、実は日常に当たり前に存在しているものである。
あのリーマンショックを経て東日本大震災を経験し、今なお直面するコロナ禍にあって、少なからず日常を失い、われわれは本当に大切なものの存在を知り得たであろうか。「平家物語」を聞くまでもなく、諸行無常を実感しているであろうか。
今回は、精神科医の神谷美恵子氏の著書「生きがいについて」(みすず書房)のなかから一部を紹介する。著者は実際に、(瀬戸内海の島にある)らいの国立療養所「長島愛生園」に滞在し、たびたび訪れて「生きがい」をテーマに一連の精神医学的な調査を行うなどしている。
その著者の結論が「わざわざ研究などしなくても、はじめからいえることは、人間がいきいきと生きていくために生きがいほど必要なものはない、という事実である」ということを深く心に刻みたい。
* * *
生きがいというものは、人間がいきいきと生きているために、空気と同じようになくてはならないものである。しかし、私たちの生きがいは損なわれやすく、奪い去られやすい。人間の生存の根底そのものに、生きがいを脅かすものが、まとわりついているためであろう。
諸行無常の鐘の声...私たち日本人の聞きなれた言葉には、この事実に対する静かな認識とあきらめが表れている。生、老、病、死。ブッダ太子を求道へと追いやった人生の四苦は、現代もなお人間生存の厳然たる事実である。
人間が、どうしても逃れえない力の重圧のもとに喘ぐような、ぎりぎりの状況をヤスパースは死、苦、浄、責、ガブリエル・マルセルは死と背信、サルトルは死と他人を挙げた。いずれにせよ、生きがいが奪い去られるような状況は、一応限界状況と呼んでいいであろう。
明るい日常生活のなかで平穏に暮らしているとき、人は人生のこのような面に本当には気がついていない。死ということ一つとってみても、パスカルにいわせれば人間は誰でも死刑囚と同じ身分にあるのだが、意識的にせよ無意識的にせよ、こういうものから眼を背け、色々なことで気を紛らせている。
周囲の人が死病にかかったり、死んだりしても、よほど身近な人でない限り、軽くやり過ごしてしまう。そうでなければ、人間の精神は一々揺さぶられて耐えられないからでもあろう。葬式のあとまたは通夜の席上、人々は思いのほか愉快そうに飲み食いし、歓談する光景はそう珍しいものではない。
あれも精神の平衡をとり戻そうとする自然現象であろう。そのなかで、故人の存在にすべてを賭けていた者は、心の一番深いところに死の痛手を負い、一人密かに呻きつづける。
人はそれぞれの生涯のなかで、違った時期に、違った形で、人生の行く手に立ち塞がるこの壁のようなものに突き当たり、その威力を思い知る。そのときには必ず生きがいということが問題になるであろう。このような悲しみと苦しみに満ちた人生もなお生きるのに値するかと。
自分はこれから何を生きがいに生きていったらよいのかと。時代がどのように変わり、政治形態や社会の仕組みがどのように改変されようとも、人生のこの面はとり除くことができないのではなないだろか。
学問や社会政策の進歩によって、病や老や死の脅威がどれほど遠ざけられたとしても、要するにそれは相対的のことでしかありえない。精神安定剤や麻酔剤で苦悩に対する感受性を低下させたり、精神賦活剤で元気をつけたりしても、結局はその場凌ぎにすぎない。
昨今は文化人類学の進歩により、人間の精神構造や意識形態、両性の役割とそれにともなう意識などが文化の相違によってかなり違うことが明らかにされてきた。各文化、各社会によって一般に採用されている価値基準が違うのであるから、それだけでも心の世界の様子が違ってくることは頷ける。
しかし、人間の最も根本的な姿を知ろうとする者にとって大切なのは、そのような相対的な差を知ることではなく、それを取り去ったあとに残る人間の共通の性質―もしそういうものがあるならば―を掘り下げることではなかろうか。
少なくとも限界状況下にある人間は、もはや文化や教養や社会的役割などの衣を纏った存在ではなく、何もかももぎ取られた素裸の「ひと」に過ぎない。死を前にしては外国人も日本人もなく、皇族も平民もなく、共産主義者も資本主義者もないのである。
どんな問題にせよ、人間のことを考えて行く上に、人間のこの面を見極めることが必要と思われるので、これからそのような状況に置かれた人々の心の世界と、その変貌を眺めて行きたいと思う。それはいわば逆光線で人生を眺めるようなことかもしれない。
しかし、病理学の発達によって生理学が進歩したように、「欠如感」を調べることによって「正常な」構造を明らかにされるところが少なくないと思う。
運命というものは、必ずしも人間にとって悪いものばかりをもたらすわけではないのだが、人間の身勝手な性質として、いいことはとにかく当たり前なこととして受け取りがちである。たとえば、私たちが悪い病気にもならず、毎日を親しい者のなかで平和に暮せるということ、それ一つを取ってみても全く不思議な「まわり合わせ」で、ただ好運というよりほかはない。
らい病にかかっている人たちをみても、なぜ私たちではなく、彼らが病まねばならないか、という問いが出てくる。伝染といってみても、確かにらいは伝染性の病ながら、極めて弱い伝染力しか持たないし、らい患者のなかには、衛生思想の高い家庭の出の人もあって、どこからあの病気を移されたのか、全く思い当たらない人も少なくないのである。
ゆえに、本当は自分の好運について平生深く思いを潜めていいはずであるのに、私たちは余程特別なことが起こらない限り、こうしたことは考えず、ただ悪運のみを深刻に受け止めるものらしい。どこの国の言葉でも、運命というのは、悪い連想を伴っていることが多いのはそのためなのであろう。
たとえばギリシャ人の想像では、三人の老いた女神モイライたちが人間ひとり一人の寿命の糸で紡いでおり、そのなかの一人アトロポスがふと気まぐれに大きな鋏でプツリと糸を断ち切ってしまえば、前途有為な青年もその場で息絶えてしまう。
その青年の母親が、「たとえ半人前の姿でもいいから息子に生きながらえてほしい。死んでしまうことは、そのことだけはどうぞ勘弁してください」と手を合わせて天に拝むような心で、永年血の滲むような看病をつづけていたとしても、ここで、彼女は一番大切な宝をもぎ取られてしまう。
恐れつづけていた最悪の事態がついに現実となってやってくれば、それをもたらしたものを恐ろしいもの、苛酷なものと受け取るのは当然であろう。客観的にみれば、それ自体善とも悪ともいえない「運命的」な現象も、このように人間の心との関係という地点からみるときには、種々な様相を帯びてくる。
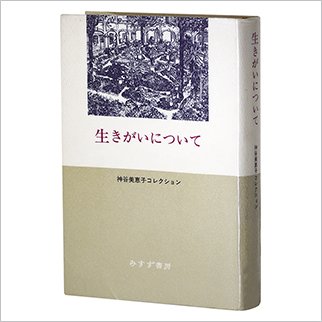
神谷美恵子(かみや みえこ)
1914年、岡山生まれ。1935年に津田英学塾卒業し、1938年渡米、1940年からコロンビア大学医学進学課程で学ぶ。1941年に東京女子医学専門学校(現・東京女子医科大学)入学し、1943年に長島愛生園で診療実習等を行う。1944年に東京女子医専を卒業後、東京大学精神科医局に入局。1952年に大阪大学医学部神経科入局。1957~72年長島愛生園精神科勤務。1960~64年に神戸女学院大学の教授。1963~76年には津田塾大学の教授。1979年10月22日に逝去。
主な著書に「人間をみつめて」(朝日新聞社)や「こころの旅」(日本評論社)、「遍歴」(みすず書房)など多数。また訳書には、マルクス・アウレリウスの「自省録」(創元社)、ジルボーグの「医学的心理学史」、ミシェル・フーコーの「臨床医学の誕生」など多数ある。







