トップページ > World View
命を慈しむ深い愛情の表れとしてのパッケージ

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
今も止まず、激化の一途をたどる、ロシアのウクライナへの軍事侵攻を避けて通れようか。目を背けていられようか。そこに在るものは、軍でもなければ武器でもない。主義主張でもなければ正と邪、敵と味方でもない。ただただ「命」の軽視であり、奪命であり、悲惨の二字に尽きる。
古の賢人は「鬼を崇むゆえに今生には国を滅ぼす、魔を尊むゆえに後生には無間獄に堕す」との言葉を残すが、「奪命」は人の心に巣くう魔であり、鬼である。かのマザーテレサは「世界の平和のために私たちにできることは?」と尋ねられ、「家に帰って家族を愛しなさい!」と答えたという。
ロシアとベラルーシの選手が出場除外となった、北京での冬季パラリンピックの開会式ではアンドルー・パーソンズIPC会長があいさつの最後に「ピース!」と叫んだ。かつて日露戦争の最中に、「旅順口包囲軍の中に在る弟を歎きて」と戦地に赴いた弟に、また強い戦争反対の意思をもって歌人の与謝野晶子が詠んだ詩「君死にたまふことなかれ」はよく知られている。
「ああ弟よ 君を泣く/君死にたもうことなかれ/末に生まれし君なれば/親の情けは勝りしも/親は刃を握らせて/人を殺せと教えしや/人を殺して死ねよとて/二十四までを育てしや」との言葉が、戦地の人の心に届かぬはずはない。
これは言葉であって言葉に非ず、遠い戦地の人命の無事をひたすら祈り、見守っている深い愛情にほかならない。今回は実業家の平川克己氏が「少しばかり趣の違うテーマ」という、文芸もののエッセイ「言葉が鍛えられる場所」(大和書房)からエルマンノ・オルミ監督の映画「木靴の樹」について触れた箇所を紹介する。
* * *
オルミ監督は、それぞれのエピソードをドキュメンタリーのような手法で撮影しています。素人の農民を役者に起用しているのも、この映画にリアリズムを与えています。いくつかの例外を除けば、農民たちは驚くほど寡黙です。
例外は、毎晩の食事のあとに、すべての家族が一堂に集まり、代表の誰かが怖い話や、昔話を聞かせるときだけです。このときは、子どもたちは目を輝かせ、話者も自分の芸の見せ所とばかりに、声に抑揚をつけて演じます。まだ、テレビがなく、ラジオも普及していない村だからこそ、こうした寄合いは貴重な情報源であり、娯楽となっているわけです。
この風景が、私たちに、どこかで見たことがあるという気にさせるのは、私たちが忘れてしまった自分たちの姿を、幾分かの慚愧と郷愁をともないながら、そこに投影することができるからではないでしょうか。
1950年代、私の実家には、工場を経営していたこともあって、周囲よりも早くテレビが入りました。毎週金曜日の晩になると、工場の2階のテレビのある部屋には、工員や近所の人々がプロレス中継を観るために集まってきました。
プロレス中継がはじまる前は、ちょうどこの映画の寄合いように、誰かが話題の中心になって、笑い合いったり、深刻な顔で話し合ったりしている光景がありました。私たち子どもは、食い入るようにして大人たちの話を聞いていたのです。
家族も、村の共同体も、私たちが生き延びていくためには、どうしても必要なものでした。プロレス中継で聞こえてくるアナウンサーの声を一つ漏らさず聞き取るために、大人たちも、私たち子どもたちも、画面に注意を集中し、眼を輝かせていたはずです。
あのとき、自分たちは、どんな眼をしていたのでしょうか。「木靴の樹」での共同体の寄合いで、身動きせずに固唾をのんで話に耳を傾けている少年や少女の眼の輝きは、工場の2階でテレビに集中していた私たち子どもの眼の輝きと同じものだったはずです。
この映画を見ていると、あの頃の自分たちが呼び戻されるように感じます。映画のなかで生きている人々に共感し、喜びを分かち合い、ともに悩んでいるのは、この映画の映像によって呼び戻された、私たちのなかの忘れ去った自分なのではないでしょうか。
原理的なことをいえば、あらゆる動物にとって、生きていくための資源は、本来すべて無償であったはずです。水も、空気も、植物も、動物も、自然からの贈与物であり、人々はその贈与を行う者に対して感謝をささげ、祈りをささげて生きていました。
自分たちが生きていくためには、動物の首を切り、血抜きをし、吊るして内蔵を抉り、肉を捌かなくてはなりません。誰よりも早く収穫するためには、肥料を工夫しなければなりません。それらのことは、人間と自然の間の直接的な交換であり、貨幣経済が介在しているわけではありません。
人間は自然の純粋な贈与物に感謝しながら生きていくほかはなかったわけです。物質的には、けして満ち足りてはいませんが共存し、饒舌ではないが明確な意志で生活を築き、自然との調和を図っていました。
その安定をかき乱すのはいつも「貨幣」であり、「技術」であり、「言葉」です。それらはすべて、交換の速度を速めるためのものでした。ベネディクト・アンダーソンがいうように、資本主義を発展させた原動力は、印刷技術の発展であり、言葉の共有による共同体の発生こそが国家の起源的形態だったのです。
近代の発展は、プリントキャピタリズムの発展を除いては考えられません。言葉の普及は、文明を推し進め、文化を生み、経済を発展させましたが、いくつかの大切なものを置き去りにしてきました。その最も大きなものは、寡黙さの価値でした。
一つは、言葉によって信頼をつくり出し、言葉によって紛争をつくり出したのです。言葉はいつも、真実とともにあるわけではありません。ときに嘘をまき散らし、相手を傷つけ、問題の種を育ててしまいます。野生の動物たちは、言葉がなく、貨幣もありませんが、生き延びる術を知っています。
貨幣も、言葉も、文明も、人間の歴史と同じだけ古く、しかも一方通行的に進化していくものです。エルマンノ・オルミは、そうした原初的な人間と自然をかき乱すものの象徴でもある、貨幣や、地主や、都市というものを声高に批判することはしません。
この映画のなかでも、それらのエピソードは背景的なものに過ぎず、前面に押し出されるのは、貧しい人々の善良さであり、優しさであり、強さです。映画のラストで、ミネクの父親が息子の壊れた木靴をつくるために、地主の樹を切ったことがばれて、一家もろとも村落共同体から追放される場面があります。
ここでも、このバティスティ家の人々の目に、不条理への怒りはなく、悲願の涙もありません。もちろん失意と不安はありますが、それが宿命でもあるかのように受け入れるしかありません。ほかの三家族が窓越しに見守るなか、ひっそりと荷物をリアカーに積んで、集落を出ていくのです。
この上なく悲惨であり、もの悲しいシーンですが、同時に不条理を受け入れながら肩を寄せ合い、お互いに助け合いながら生き延びていく家族の、強さも感じます。追放される家族のやりきれなさにも、それを見守るほかの家族の切なさや不安に対しても、救いの手は差し伸べられません。
人生は残酷であり、不条理に満ちていますが、それらを見つめる視線には、その残酷さや不条理を生きる人々に対する深い愛情があります。オルミ監督のカメラこそが、その視線であり、無感情なドキュメンタリーのように、この光景を追っていくのですが、視線の先には常に深い愛情が注がれています。
この作品を観る観客の視線も、この監督の視線と一体化し、もはや傍観者であることを離れて、彼らの隣人のように、窓の隙間から追放される家族の行く末を案じているのです。
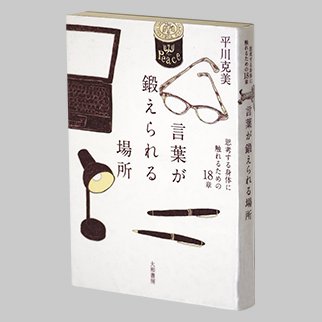
平川克美(ひらかわかつみ)
1950年7月、東京生まれ。1975年に早稲田大学理工学部機械工学科を卒業後、1977年に内田樹氏らと、翻訳を主業務とするアーバン・トラストレーションを設立し、1999年にシリコンバレーのBusiness Cafe Inc.の設立に参加。2001年にリナックスカフェを設立し代表取締役に就任。、2014年に隣町珈琲店主、ラジオカフェ代表取締役、立教大学客員教授、早稲田大学講師。
主な著書に「移行的乱世の思考―誰も経験したことがない時代をどう生きるか」(PHP研究所)、「小商いのすすめ」(ミシマ社)、「俺に似たひと」(医学書院)、「株式会社という病」(文藝春秋)など。







