トップページ > World View
思索のとき----「責任を持っている」ことの意味

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
本来は祝福されて、希望として誰もが心を満たしてゆくべきものが、悉く矮小化され、嫌忌されるものともなりつつある。これは由々しきことである。とはいえ、こうしたことは今に始まったことではなかろう。これまでは経済といった波に隠れていたものが、波が引き始めて誰の目にも露になってきたのだ。
どうしても人の目はコスト(カネ)へと向きがちとなるのだが、問題の本質はその人の"目"であり、"目"の根にあるものだと思う。ゆえに表層的に観ていたのでは問題の解決には至らず、遠回りのようでも深く問題の本質にあたる思索が必要である。
たとえば、すぐに責任の所在などを問われがちだが、かのナイチンゲールなどはこんな言葉を残している。「大事小事を問わず、何かに対して『責任をもっている』ということの意味を理解しているひとは----責任をどのように遂行するかと知っている人という意味なのである」というものだ。
しかも、それを知る人は「男性でも、女性でさえも、なんと少ないことであろう」と慨嘆している。つまり「今に始ったこと」ではなく、昔からわれわれひとり一人の心に巣くっている問題なのである。
そうした意味でひとり一人が、またあらゆる分野(包装においても)で問い直さなければならない問題である。今回は、「新国立競技場建設問題」について、自らの課題として一段深い問い掛けを放っている、建築家の槇文彦氏と大野秀敏氏編著の「新国立競技場、何が問題か----オリンピックの17日間と神宮の杜の100年」(平凡社)からその一部を紹介したい。
東京屈指を誇る外苑の歴史的景観や市民の憩いの場としての建築とは何か。建築界や市民社会に問題を投げかけたシンポジウムの内容を中心に、エッセイ・論考といったかたちでまとめた一書である。
* * *
今後、日本では人口、とくに若年層の人口が急激に減少しますし、環境問題も重くのしかかっています。また、どの先進諸国もかつてのような経済成長ができず、中央銀行が金利を操作したりお札を刷る政策でしのぐという非常に閉鎖した状況にあります。
この困難な状況は一朝一夕には変えることはできないだろうと思います。どこの地域でも、少ない選択肢と少ない資源で、どうやって人々の生活の水準を下げずに、やっていくか、このことを目指して知恵を絞っている。なのに、今回のオリンピック計画をみると、1964年のオリンピックの「夢をもう一度」みたいな気分を感じてしまいます。
1964年のオリンピック(10月10日開会式)を迎えるために、東京を中心に日本は大改造されました。新幹線は直前の10月1日に開業しています。日本で初の都市間高速道路である名神高速道路も開通しました。東京では羽田空港と都心を結ぶために東京モノレールが造られ、六本木通りなどで道路拡幅もされました。
首都高速道路網も急速に広がりました。もう一度、車のたとえですが、ターボチャージャーを付けたように一気に加速しました。それは大成功だったといってもいいでしょう。何故なら、日本はその当時、人口構成上も若かっただけでなく平均9%以上の経済成長率で高度経済成長の真っ最中でした。
当時は未だ所得も低く、国内の施設整備も途上でした。そこに油を注いだように一気に燃え上がったというわけです。しかし、今度のオリンピックを迎える2020年は全く事情が異なります。今後は、東京も人口が減り、日本の全体の活動量もだんだん鈍ってきます。
70年間で人口総数は確かに2割増しになっていますが、子ども数は半減しています。さらにオリンピックから30年経った2050年になると、総人口は先のオリンピック当時の水準に戻っていますが、構成が全く違っています。子どもは3分の1に減り大人も8割近くまで減っています。
つまり高齢者だけが増えるのです。国が成熟社会になっているというのに、1964年のときと同じようなターボチャージャーの付いたスーパーカーを買って走りまくると、きっと交通事故を起こすだろう、というのが懸念の大きなところです。
景観の話に限定しますと、東京あるいは、日本というところは非常にむずかしい場所だと思います。何がむずかしいかというと、モザイク状にいろいろな風景が入り交じっているからです。明治まではわりと安定していました。有史以来ずっと中国をお手本としながらも、交流と断絶が交互にあって、よい形で日本化を果しました。
明治維新で、日本は文明のお手本を大々的に中国から西洋に切り替えました。19世紀の西欧は、都市ではパリが最高度に完成され、建築では西欧から植民地の建築まで様々な様式を使い分けるという時代でした。日本の大学でも学生たちは、西欧の様式建築を習いました。
東京駅や明治生命ビルや赤坂迎賓館はこの時代の建築です。一時は、公的な建築は皆洋風というところまで進みました。一方、その間に立つ住宅は、江戸時代からあまり変わらない構えでした。和洋チャンポンの都市景観ですね。日本では明治から大正になるころ、欧米で新しい建築が生まれ、日本の建築家たちもすぐに反応しました。
和洋チャンポンの都市景観はほとんど空襲で焼けてしまいましたから、この新しい建築、つまり近代建築で戦災復興が進みました。こうした、日本の街には、お互いに相容れないような、江戸建築、19世紀欧風建築、近代建築、そして現代建築と、いろいろな景観がモザイクのように錯綜しているのです。
なぜかというと、西洋は18世紀、19世紀、20世紀、世界の文明の中心にありましたので、日本のように基準を外に求めて右往左往しなかったからです。おおよそ、自分たちがいままでやってきた通りにやればよかった。では、東京のようなモザイク都市で、都市景観というのはどう考えればよいのか。
1つは、この際だからもっと刺激的なモザイクにしようという方向です。いつも異質であるもの、目立つものを造りつづけることになります。しかし、この方向は相当レベルの高い異質物を投入しつづけないと、単なる混乱の極みになる可能性が高い。
とくに建築にお金を掛けられない地方都市や郊外や場末に行くと悲惨なことになります。つまり、日本の現状です。もう1つの考え方は都市に建築を造ることをすべて増築であると考えることです。
今回、槇文彦さんが異議申し立てをされた。槇さんには長年の建築家の経験があり、体育館もたくさんやっておられ、加えて隣接する千駄ヶ谷の東京体育館の設計をやられています。
だから、体育館のスケールや外苑のあたりの土地勘を豊富にお持ちだったのだと思いますが、あの案をみて、この建物のスケールには非常に問題があると、瞬時に反応されたのだと思うんです。先ほどの、宮台真司さんの原発の話にもありましたけれど、民主主義社会は誰でもモノをいっていい社会です。
それが高じて、みんな「上から目線」というのをひどく嫌って、誰もが「みんなの目線」でモノをいわなきゃならないような風潮になってきています。しかし、やはり専門家、なかでも「関わりを持った専門家」は、同じ専門家でも見通しの射程距離が違うことを、今回、槇さんに見せていただきました。
非常に強い責任感をお持ちになって、非常にスピーディに行動されたことに、専門家のあり得べき姿----民主主義社会における「多数決」だけではない----専門家とはいったい何をするんだ、という姿を見た思いがします。建築の専門家であるからといって、どこかのプロジェクトで間違いがあるからといって、その度に乗り出していくなんてことはとてもできないわけです。
けれども、関わりを持ったプロジェクトに対しては、ある種の責任感があるということが、ここで示された、ということを非常に強く感じたわけです。槇さんは、そもそも、市民社会がどうあるべきかというテーマ、市民社会のなかに建築がどうなくてはならないのかというテーマを、もっとも真剣に考えられてきた建築家の人だと私は思っています。
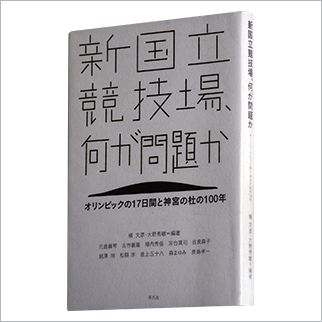
槇氏は、日本建築家協会の機関誌「JIA MAGAZINE」(2013年8月号)に「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈で考える」との一文を寄せた。
(※)槇文彦…日本の建築家。
(※)宮台真司…社会学者(社会学博士)、首都大学東京教授。
大野秀敏(おおのひでとし)
1949年に岐阜市に生まれる。1972年に東京大学工学部建築学科卒業、1975年に東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了。中野恒明とともにアプル総合計画事務所設立。2005年より吉田明弘をパートナーに、アプルデザインワークショプに改組。日本の建築家。元東京大学大学院教授(新領域創成科学研究科環境学専攻、工学部建築学科兼担)







