トップページ > World View
パッケージの映し出す豊かな生活感情
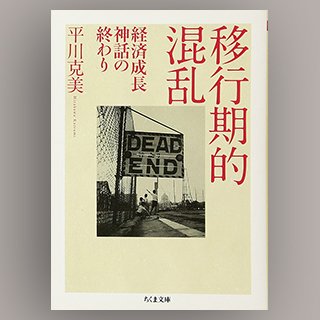
はや、七十二候の「水始涸」(みずはじめてかるる)のころである。秋分の末候とはいえまた残暑のつづく日々だが、それでも秋は深まっていくものである。「七十二候」とは、二十四節気を初候と次候と末候の3つに分け、四季の移ろいを表わす言葉である。
一時は小売店舗の棚から姿を消した精米だが、(だいぶ売価は上がっているが)ようやく新米が棚に並びはじめた。日本のような稲作地では、「水始涸」は田から水を抜き、稲刈りに備えるころと解釈される。ただ「礼記月令」「淮南子」などに「陰気益々強くなり水涸る」と記される起源は、乾き枯色となる秋の情景を表わす言葉のようだ。
「落水」は出穂後の約30日で、40〜50日後に稲刈りされるのが通常だが、稲が実っておいしくなるのは落水から10~20日間の登熟期間で、それには秋の残暑は欠かせない要素である。日中の気温が高く夜が冷え込む寒暖差が、お米をおいしくさせる要素である。
2023年度産は猛暑で新米の品質に影響が出たが、2024年度産は「近年稀にみる良い出来の新米」といった声が各地の農家から聞かれる。また専門家によれば、精米の一時的な品薄は流通プロセスの目詰まりが要因で、新米が出て品薄は解消されてもしばらくは、その穴埋めで高値はつづくが、10月末になれば流通量も安定し価格も落ち着くとの見方である。
「親孝行したいときには親はなし」とのことわざもあるが、あの松下幸之助氏でさえも「親が亡くなってのち、せめて少しでも孝行しておいたらと悔やまれる」と、亡くしてはじめて親のありがたみを知るわけである。比肩するものではないが、失ってみてはじめて「お米」のありがたみを知った人も多かろう。お米以外にも食べ物に事欠かない現在では、なかなか実感が湧かないかもしれないが、「白米は白米にはあらず、即ち命なり」である。今回は、実業家の平川克美氏の著書「移行期的混乱〜経済成長神話の終わり〜」(ちくま文庫)から、その一部を紹介する。
* * *
お会いした小関(智弘)さんからは、当時の工場の雰囲気や下丸子や大森といった工場外の文化サークルのお話をお聞きし、記憶の彼方に霞んでいる1960年代の場末の町で働く人々の生活感情が、思いのほか豊かなものであったということを教えていただいた。あえていえば、それは「お気楽な」日々でさえあったのだ。
「当時は、まだ仕事というものがよく分かっていなかった。ところが、30(歳)を過ぎて、ある工場でFさんという優れた旋盤工の隣で、並んで作業をすることになりました。その経験が私に、仕事とは何かということを徹底的に教えてくれる契機になりました。
それまでは、適当に稼いで食っていければいい。仕事は家族を養っていく手段に過ぎない。大事なのは社会を変革することだというので、政治活動のようなことばかりに力を注いでいました。ところが、Fさんの仕事振りをみて、これは凄い人だと思いました。
これまで私は、とんでもない思い違いをしていたのかもしれない。これまでも優れた旋盤工はたくさん見てきましたが、Fさんは単に器用だとかいうのではない。仕事に対する凄みというものがあり、とにかくこの人に追いつていこうということで、はじめて本気になってがむしゃらに仕事をしたのです。そうして鉄を削るという仕事の奥の深さに気付かされたのです」
会社のためでもない、家族のためでもない、社会のためでもない。ただ、目の前の機械、加工を待つ鉄の塊、目の前の「仕事」がなにものかからの召命であるかのように、徹底的に取り組み、没頭する日々。そういうことが、確かにあるのだということが、当時の自分の身体感覚を確かめるかのように語る小関さんから伝わってきた。
しかし、当時の町工場のなかには、お気楽に日々を継いでいる人々がいる一方で、意識するにせよしないにせよ、徹底的に仕事にのめり込んだ人々が少なからずいた。私は「昨晩も夜なべだったよ」という何度も聞かされた父親の言葉を思い出す。
「それが働くことと、生きることが同義であるような人々なのですね」と、私は以前、小関さんから頂いたお手紙のなかに書かれた言葉を口にした。それは、あるとき池上本門寺の近くのテーラーに背広をつくりに行ったときの話である。
テーラーの親父が、一通り採寸を済ませたあとで「あなた、ひっとして旋盤工ですか」といったのだという。「旋盤工は、左肩が下がるんですよ。足も踏ん張るので、ガニまたになっちゃってね」。小関さんも凄ければ、この洋服屋もまた凄い。
私の父親は、右手の人差し指と中指は第一関節のところで切断されている。左手の中指も同様である。プレス屋にとっては指を落すことはほとんど、勲章のようなものであったのかもしれない。
こういった逸話が示しているのは、日本の高度経済成長の底辺には、自分の身体が変形するほどに、仕事にのめり込み、打ち込む人々が少なからずいたということであり、それはまた当時の多くの日本人が、こういった仕事観を当然のように共有していたということでもある。
この、仕事に対する強固な意識は、必ずしも、すべての国の産業労働者に共通に顕れるものだとはいいがたい。むしろ、すぐれて日本に特殊な考え方であったといわなければならないと思う。
たとえば「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」のなかで、マックス・ウェーバーが引用したベンジャミン・フランクリンの言葉と比較してみれば、その違いは明らかであろう。
「時間は貨幣だということを忘れてはいけない。1日の労働で10シリング儲けられるのに、外出したり、室内で怠けていて半日を過ごすとすれば、娯楽や懶惰のためにはたとえ6ペンスしか支払っていないとしても、それを勘定に入れるだけではいけない。本当は、そのほかに5シリングの貨幣を支払っているか、むしろ捨てているのだ」
この引用部分は、ベンジャミン・フランクリンが1736年に書いた「金持ちになるために必要なヒント」に拠っており、まさに近代資本主義発展史の劈頭にこのような労働観がアメリカ人に刷り込まれていたことを示す好例となっている。
フランクリンにとって労働は貨幣と等価で交換されるものであり、貨幣は労働の象徴であると考えられている。この思想(反知性主義といってもよいだろう)の根底にあるのは、貨幣に対する信用であり、尊敬なのだ。
先の小関さんの言葉や、大田区池上の仕立て屋のエピソードからは、貨幣に対する尊敬といった匂いを嗅ぎ出すことはできない。むしろ逆である。どちらの場合も仕事を1つの召命としてとらえてはいるが、フランクリンが貨幣という表象によってそれを表現したのに対して、日本人の場合には労働をする人間に対する尊敬であり、それを貨幣によって表象することはむしろ退けられていたというべきであろう。
つまり、労働は何ものにも表象されないがゆえに(何ものもそれに取って代わることができないほどに)尊いと考えられていたと思うべきなのだ。このことはまた、私たち自身に馴染みのある「お茶碗に盛られたご飯のひと粒をもムダにしてはならない」という親の説教が教えた倹約の精神と、フランクリンが説く倹約の精神との違いにもよく表れている。
(※)小関智弘...ノンフィクション作家。著書に「粋な旋盤工」(1975)、「春は鉄までが匂った」(1979)、「大森界隈職人往来」(1981)、「鉄を削る 町工場の技術」(1985)、「町工場の磁界」(1986)、「羽田浦地図」(2003)など。

平川克美(ひらかわ かつみ)
1950年7月、東京都生まれ。東京都立小山台高等学校を経て、1975年に早稲田大学理工学部機械工学科を卒業。1977年に渋谷区道玄坂に翻訳を主業務とするアーバン・トランスレーションを内田樹とともに設立、代表取締役となる。2001年5月にリナックスカフェを設立し代表取締役に就任。2011年4月に立教大学の特任教授。2014年3月に隣町珈琲店主。2016年4月に立教大学の客員教授、早稲田大学の講師を務める。
主な著書に「経済成長という病」(2009年)、「言葉が鍛えられる場所」(2016年)など。







