トップページ > World View
コロナ禍の欠伸うつして日永かな

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
拡大と収束とをくり返し、もう3年を越えたコロナ禍で実感することは、今を生きることの大切さである。「今を生きる」とは、日々の生活と向き合うことでもある。いまや世界共通語でもある「HAIKU」は、正しく生活と真摯に向き合うことで生まれる詩心であり、文化といえる。
今回は、そんな「俳句」に欠かせない歳時記の季語をテーマにした、作家の川上弘美氏の随筆「わたしの好きな季語」(NHK出版)から、秋の季語をテーマにした3つ(「天の川」「枝豆」「瓢」)を選んで紹介する。
【天の川】
「昔」、と書きかけて、「昔って、どのくらいだろうか」と、考え込みました。「十年ひと昔」といういい方があるならば、わたしが生まれてからすでに六昔以上過ぎているわけで、それならば小さいころの話は、堂々とした「昔」だなと、安心しました。
いや、文章上は「安心」ですが、実際の心は「そんな昔の人間なんだ、わたし...」と、少しびっくり。はい。時々する、昔の話を、今回もいたします。
育ったのは、東京二十三区内でした。家からは天の川が見えました。タヌキやイタチがぼっこしていました。
カブトムシはわさわさ捕れました。運動会の徒競走のスターは足袋で走っていました。お手洗いはポットンでした。「三丁目の夕日」の世界よりも、さらに東京都心から離れている感じでした。そうなのです。東京でも、天の川が見えたのです。という話も、以前しましたね。
ところがある日、おない歳で、東京の真ん中、新橋育ちの知人が、いったのです。
「カワカミさんは東京育ちだから、天の川なんて見たことがないでしょう。野外でキャンプするのなんかも苦手そうだし」
「いえいえ、天の川、たびたび見ましたよ」
答えると、知人はふうんといい、
「じゃあ、お母さんかお父さんの故郷かどこかで?」
と聞くではありませんか。いいえ、東京の実家から見えましたよ。え、まさか。東京じゃあ、天の川なんか見えるわけないでしょ、わはは。でも...。
というようなやり取りがつづき、なるほど同じ東京でもわたしの住んでいた場所は自然に恵まれていたのだなあ(あるいは、開発が進んでいなかったのだなあ)と、複雑な気分に。
天の川を銀河ともいうのだと知ったのは、中学に入ってからです。確かに銀の河だと感心したものでしたが、そのころくらいから、天の川はわたしの家からは見えなくなりました。
荒海や佐渡に横たふ天河
/松尾芭蕉
夏の夜、天空を横切る天の川の、あまりに多い星の数にくらくらした記憶は、今も鮮やかなんですがね。
【枝豆】
秋の季語・意外ベストスリーと、わたしが呼んでいます。すなわち、朝顔、枝豆、西瓜。この三つ、正真正銘、秋の季語なのです。どれも夏ど真ん中のもの、という印象にもかかわらず。でも、よく考えると、朝顔が咲くのは、宿題で育てた記憶をたどると、確か夏休みの終わりごろでした。
枝豆も、だだ茶豆は八月に入ってからが最盛期のような気がします。西瓜だけは、少しでも熱くなったらすぐさま買いに走るわたしですが、昭和のころの夏を思い出してみれば、一番よく食べたのは、八月のお盆前後だったのではないでしょうか。
歳時記での夏は、八月のはじめ、立秋の前日でおしまいです。立秋は、たいがい八月七日。感覚的にはまだまだ夏の真ん中なのに、八月七日過ぎは、歴の上では秋、ということになってしまうのです。
それならば、朝顔も枝豆も西瓜も、秋のものなのかもと、一瞬は納得するのですが、同じ秋でも、十月や十一月過ぎといった、秋も深まる時期には、この三つ、まったく似合いません。いわば、限定的な初秋の季語、とでもいえばいいでしょうか。
さて、わたしは枝豆が、ともかく好きなのです。歳時記など無視して、六月の出始めから、十月の出終わりまで、八百屋さんの店先に出ているかぎり、食べつづけます。ちなみに、枝豆の茹で方には、そのときどきのマイブームがあります。
柔らか茹で期 → 固茹で期 → 気まぐれ期
このサイクルを、二週間周期くらいで繰り返すのです。塩の具合も、また色々。食べる直前に茹でるか、それとも前日に茹でて塩味をしっかり浸み込ませるか、ということもあります。
それらを組み合わせると、十通り以上の茹で方と味つけ方があり、さらに枝豆の種類によっても、味はかなり変わってくるわけです。数カ月間食べつづけても、けして飽きないゆえんでありましょう。
枝豆や三寸飛んで口に入る
/正岡子規
【瓢】
「瓢」と書いて「ふくべ」と読みます。瓢箪(ひょうたん)のことです。ほかに、「ひさご」といういい方もあって、「ひさご」「ふくべ」という名の居酒屋をときおり見かけます。瓢箪は古来、飲料−−わけてもお酒を満たしておく容器として使われることが、多かったからでしょうか。
「ふくべ」という響きを聞くと、わたしは「なんだかエッチだなあ」と、瞬間思ってしまうのです。たぶんそれは、「ふぐり」という響きを連想させること、そして、瓢箪の形そのものが、同じく「ふぐり」を思わせることが、理由です。
「エッチ」といっても、まあ、小学男子くらいのレベルのエッチですね。小学生といえば、昔通っていた小学校の裏庭には、金属のフェンスが巡らせてあり、そのフェンスには蔓植物が絡まっているのでした。冬には枯れてしまう蔓でした。
かぼちゃの葉に似ているけれど、もう少し小さめのせいせいした青葉を茂らせるその蔓植物は、初夏になると白い花を咲かせます。いったい、どんな実がなるんだろう。毎年思うのですが、そうするうちに夏休みに入ってしまい、二学期になって登校してくると、花はとっくに萎み、実は見当たらないのです。
実のならない植物なのかな、とあきらめかけて、やがて四年生になったときに、その蔓植物が何だったか、判明することとなります。四年生の夏休みは、学校にプールができた年でした。いつもならば来ることのない夏期休暇中の学校に、プール開放の日は入ることができ、それはとてもウキウキすることでした。
プールの時間が終わり、着替えてなんとなく裏庭の辺りをウロウロしていると、用務員のおじさんが、蔓に下がっている実を、鋏でパチンパチンと伐っているではないですか。蔓は、瓢箪の蔓だったのです。
「一つ、あげようか?」
用務員さんはいいました。
こっくりすると、おじさんはわたしの手のひらの上に、青い青い小さな瓢箪を、そっとのせてくれました。
ふくべ棚ふくべ下りて事もなし
/高浜虚子
本当に「事もなし」というふうな、蝉の鳴く、平和で気だるい昭和の午後でした。
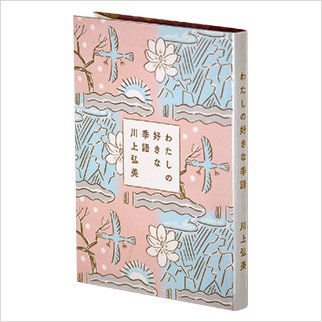
川上弘美(かわかみ ひろみ)
1958年、東京生れ。雙葉中学校・高等学校を卒業後、お茶の水女子大学理学部生物学科に入学し、SF研究会に所属。1980年に卒業し、母校で生物の教員となる。1986年に退職し、結婚・出産ののち主婦を経て、1994年に「神様」で第1回パスカル短篇文学新人賞を受賞。
1996年に「蛇を踏む」で芥川賞、1999年に「神様」でドゥマゴ文学賞、紫式部文学賞、2000年に「溺レる」で伊藤整文学賞、女流文学賞、2001年に「センセイの鞄」で谷崎潤一郎賞、2007年に「真鶴」で芸術選奨文部科学大臣賞、2015年に「水声」で読売文学賞、2016年も「大きな鳥にさらわれないよう」で泉鏡花文学賞を受賞。
そのほかにも「椰子・椰子」「おめでとう」「ニシノユキヒコの恋と冒険」「古道具中野商店」「猫を拾いに」「ぼくの死体をよろしくたのむ」「某」「三度目の恋」などの作品がある。







