トップページ > World View
巨大な生命の循環(自然)に加わる包装

今月はインタビューをお休みし、特別編として「WORLD VIEW」を掲載いたします。
「エダモン」の愛称で知られる、料理研究家の枝元なほみさんは、或るエッセイのなかでこんなことをつづっている。「あるとき、丘の上で転んだ。ペタンコの靴が脱げて靴下が少し破れた。そのとき私、『あっ、地に足がついた』と思ったのだ。ほんとは、足に土がついたんだけどね」と。
彼女は常々「地に足の着いた暮らしがしたいものです」と、冗談めかしていっているようで、そのときに「あれ、足に土が着いたのなんて何年ぶりだろう」と思ったようである。「そうかむずかしく考えずに、暖かくなったら畑でも田んぼでも草原でもいい、靴も靴下も脱いで裸足で立って、地に足を着けてみよう!」と、彼女はいう。
簡単にできることほど、(むずかしく考え)やりそびれがちである。随分と前の夏の夜のことだが、だいぶ遅い帰宅の途中で疲れてか、近くの親水公園の緑地に寝そべったことがある。辺りは真っ暗で虫の音が響き、ヒンヤリとした緑地は心地よく10分ほど眠りに落ちたことがある。
ふっと目覚めると(気のせいか)疲れが取れ、身が軽くなったような感じがした。あのとき、土から立ち昇るエネルギーに包まれた不思議な感覚を、今でも憶えている。われわれ生物および生活は、生物(有機物)と無生物(無機物)によってつくられた土壌で成り立っているのである。
「地に足の着いた暮らし」とは、その実感にほかならぬ。いわば、われわれの生活即土壌であり、われわれ自身および生活は地球の一部である。生物同士が互いにいがみ合い、争って土壌を蔑ろにしては全く意味がない。農業科学研究所所長の中嶋常允氏は「土は生物を媒介としてはじめて土壌となり、生命を育む力をもつ」という。
今回は、その中嶋農法の創始者でもある中嶋常允氏の著書「土といのち―微量ミネラルと人間の健康」(地湧社)から一部(いのちは非合理の合理)を紹介したい。
* * *
人は、急病をわずらうか、身近な人の死に遭遇したとき、命を思い出す。しかし普段から命は一瞬一瞬に死と対決して存在していることを感じている人はあまりないようです。
われわれが生きていく上で、生命体としての働きには正常値と異常値がありますが、正常値というものには或る幅があります。そして、その幅の間を人間の機能は意志とは関係なく自動的に調整され、コントロールされています。
しかし、これは正常な環境で、バランスの取れた栄養を適切に供給され、適切な代謝が行われて、適切に排泄されているときの話です。ところが、ご存知のように、今日の食事は色々な意味でアンバランスになってきていますから、人間の健康を保つ機能にも狂いが出はじめているのです。
その大きな理由の一つに、栽培作物それ自体が、自然循環の輪から切断されているということが挙げられます。人為的に栽培条件を調えることは可能であると考え、経済優先の命を前提にしない現代農学は、ひたすら質より量を目的としているので、事態はますます深刻になっています。
では、なぜそのようなことになったのでしょうか。1843年から約20年間、ドイツの化学者リービッヒと、イギリス化学者ジョン・ローズ(ロザムステッド農事試験場の初代場長)との間に、有名な論争が行われました。当時、ゲセッツ・デス・ミニスムス(最小養分律)を説いたリービッヒが共に最も重要視していたのは、いかにして収穫を増大させるかということでした。
ローズは特定の植物栄養素を与えたときに収穫量が増大すれば、それが一番よい肥料だと考え、それをアンモニアだとしました。一方、リービッヒは欠乏しているものに目をつけましたが、要するに肥料の良し悪しを全て、収穫量をもって計ったのです。
結局、この論争ではリービッヒが負けて、ローズが勝ちました。その当時のアンモニアといえば、アンチョビ(小さな鰯)を食べるグアノ鳥がつくり出した堆積物でグアノと呼ばれる動植物性の、生き物全体が含まれている有機質肥料でした。
ところが時代が進み、化学の発展にともなって、空中の窒素を固定化する方法が発明され、グアノのような総合的な有機質肥料にかわって無機質の硫酸アンモニア肥料が合成されて使われるようになりました。
リービッヒはこの論争に加わったため、今日あたかも無機化学肥料の推進者の一人であったからのようにいわれていますが、東京大学名誉教授・椎名重明先生の解説によれば、リービッヒは「植物の生命活動に関与する土壌、水、空気などのすべての成分と、植物体および動物体を構成する諸成分との間には相互関連があり、しかも、無機質類の有機体的活動の担い手への変化を媒介する全体的な関連の鎖の輪が、一つでも欠けるようなことがあれば、植物も動物も存在しえなくなる」といっているのです。
しかもリービッヒは、その当時の中国および日本の有畜複合経営の完熟堆肥施用による循環農業が世界中で最も理想的な農業形態であると喝破しているのです。
然るに世界の農業の流れは、ローズが論争に勝ったため、窒素肥料重視の流れを基底して、自然の命と離れて拡がっていったのです。その結果、今日の不健康な生育を増長し、病虫害の多発を招き、農薬の異常なまでの多用が平常化する事態となっているのです。
そして、われわれは栄養もアンバランスで、生命力の弱い、このような作物を直接または加工原料として使用した食品を常食せざるを得ない状態に置かれているのです。今日の文明は量的増大が第一目的でありますから、人間も身長体重は増加したけれども、体質は低下しているのであろうと思われるのです。
悪質な伝染病と細菌性の疾患は、医薬の急速な進歩によってほぼ封殺することができましたが、退行性の成人病、慢性病は増加する一方です。この現象はついには成人から小児へ、小児から幼児へと移行し始めており、また出生児の奇形の発生率も段々増加の一途をたどっています。
ある医学者の話によると、男性の精子の遺伝子にも奇形が多くなったそうですが、こういう話を聞くと前途は憂慮にたえません。物質文明は日進月歩をくり返し、動かすべき手足も段々動かさなくなり、室内環境は夏の暑さも、冬の寒さも感じさせないほど調整され、農作業も工場労働も、機械化とロボット化が進み、重労働はなくなって快適になっています。
これもわれわれの命の存続にとっては好ましからざるもののようです。命は非合理の合理として超合理の存在なのであります。たとえばここに革靴がある。
革靴を履いて歩いていけば、革靴の底の皮は段々と薄くなっていきます。しかし、裸足で毎日歩いているとき、足の皮は段々と厚くなってきます。命の無いなめし皮には合理性が働き、命のある裸足の皮には非合理の合理性が働くのです。命は鍛えなければ強くならないのです。
楽をすると命は弱くなるのです。そして機能は退行していきます。人間の能力は、苦難に遭遇するたびに強められ啓発されていくものです。その苦難や困難に耐える体力というのは、自然に近いミネラルバランスの体質を維持することによって保たれるのです。
孔子は論語のなかに、「粗食を食らい、粗衣をまとい、肱を枕にして楽しみまたそのなかにあり」といっていますが、この粗食は窒素多肥によってつくられた今日的食糧ではなく、自然循環のなかでミネラルバランスの取れた粗食だから精神的安定が得られたし、その結果、血液循環が良いので暖衣なくとも粗衣のままで自然環境に順応できたのだと思われます。
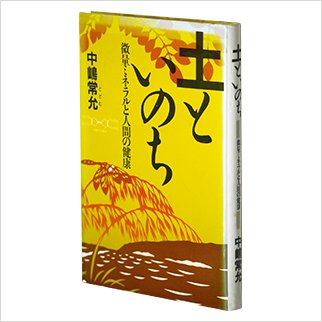
中嶋常允(なかじま とどむ)
1920年、熊本県生まれ。1943年に明治大學商科を卒業し、1952年に葉緑素と血色素の構造及び核の類似を発見、苦土肥料開発、1955年に英・ローザムステッド刊「植物微量要素欠乏診断」の写真に興味を覚え「土壌科学研究所」を設立、土壌分析を開始。1959年に「農業科学研究所」と改称し、植物栄養としてのミネラルの研究を開始し、農家の土壌分析診断処方(施肥設計)を始める。
1987年に、日本綜合医学会副会長に就任、1991年に科学技術庁長官賞を受賞、1998年にNPO法人日本綜合医学会理事長に就任する。2000年に食品産業功労賞を受賞し、2006年に農林水産技術情報協会理事長賞を受賞し、2007年に日本綜合医学会最高顧問に就任する。
著書に、地湧社の「はじめに土あり」「土を知る」や文理書院の「間違いだらけの有機農法」などがある。







