トップページ > World View
昆虫の造形の美しさに着目したパッケージ

2024年の新語・流行語大賞の年間大賞には、昭和から令和にタイムスリップした主人公が、価値観の違いに戸惑いながら奮闘する姿をコミカルに描いた民放のテレビドラマ「不適切にもほどがある!」の略称の「ふてほど」が選ばれた。
この「ふてほど」については、選考理由などには挙がらない、時代性を踏まえた社会的な意味を考えてみるのもおもしろい。ただ専門でもなく紙幅の都合もあり、それは他紙に譲ることとする。さて、流行語とは呼びづらいものだが、分野を問わず「地政学的」との言葉が多用されるようになってきた。
それはウクライナ危機やガザ地区での戦闘に起因していることはいうまでもない。2022年、タモリ氏のいった「新しい戦前」が話題となったが、今や「戦時下」といえばいい過ぎだろうか。地理と政治学を組み合わせた用語である「地政学」は本来、地理的な条件に基づく国家間の政治や経済、軍事戦略を分析する学問である。
だが、「戦時下」を意識した「地政学的」では、もはや学問領域ではなく現実のリスク要因を指すものだ。故・安倍晋三氏は首相時代に「地球儀を俯瞰する外交」を標ぼうしていた。故人を貶めるつもりはないが、「地球儀」は本来俯瞰する対象で、いうならば「地球を俯瞰する外交」である。
ただ「地球儀を俯瞰する外交」は「地政学的な戦略外交」とも解せなくはなく、戦時に至らせないための「積極的平和主義」の平和外交であったとすれば、道半ばであったことは悔やまれる。だが、それもまた人為に過ぎず、ここらで人為ではない地政学的な視座を取り入れてみることも大事である。
では、人為ではない視座とは何か。「NHKラジオ子ども科学電話相談」でも人気の昆虫学者・丸山宗利氏は「ヒトも所詮、数えきれないほどの生物種のなかの一種に過ぎない。たとえば昆虫は、知られているだけでも世界に100万種を数え、地球上に生活する生物種の大部分を占めている」という。
今回は、新春号でもありがらりと視点を変え、丸山氏の著書「昆虫はすごい」(光文社新書)からその一部分を紹介したい。「偶にアルバイトに来る学部生は、小学5年生のときにこれ(「昆虫はすごい」)を読んで昆虫を研究したいと思い九大に進学したとのこと。嬉しさとともに時間の経過を実感させられる」と丸山氏(Xより)。
* * *
昆虫とヒトとの関係は、農業害虫や衛生上の害虫、不快な害虫のように、ヒトに対して負の影響を与えるばかりではない。ヒトが昆虫に恩恵を受けている例もたくさんある。とくにヒトの生活に重要な昆虫は、カイコとセイヨウミツバチだろう。
それぞれ絹糸と蜂蜜の生産に欠かせない昆虫である。カイコは昆虫で唯一の完全な家畜昆虫で、イモムシである幼虫は、餌を探して歩き回ることをせず、成虫も飛ぶことがない。このような性質から、野外で生きることは不可能といわれている。
カイコを育てることを養蚕というが、その歴史は長く、はじまりは五千年前にさかのぼるという。もともとは日本にもいるクワゴという野生のガを中国で飼育し、品種改良したものという説が有力である。
一方、蜂蜜を生産するセイヨウミツバチは野生のハチの巣を巣箱に入れ、半野生状態で野外飼育しているものである。野生化しても生きていけるが、より多くの密を生産するようヒトによって品種改良が進んでいる。
日本にはもともとニホンミツバチというハチがおり、それもときに飼育されるが、セイヨウミツバチより管理がむずかしく、一般的ではない。熱帯アジアや南米ではハリナシバチというミツバチの仲間を飼育して蜜を採取しているところもある。
ミツバチは蜜以外にも利用価値があり、蜜集めの際に花から花へと花粉を運ぶことから、植物の受粉にも大きく寄与している。ただし日本にもともと生息していなかったセイヨウミツバチについては、日本在来の花に来るハチに対する影響(競争関係)が心配される。
昆虫はときに食べ物として利用されることもある。もともと人類の祖先は、かなり古い時期から昆虫を食料としていたと推測されており、現代人が昆虫を食べたとしても何ら不思議ではない。また実は、多くの昆虫は食用にすることが可能である。
先に紹介したカイコも、繭から絹を取ったあとに残る蛹を食べることもある。ラオスやタイ北部など、いまだに昆虫を重要な食料源としている国や地域も少なくない。日本全体ではイナゴの佃煮が比較的一般的であり、昆虫食の盛んな長野や内陸地方では、ほかにも様々な昆虫が食用に利用される。
とくに有名なのはクロスズメバチの幼虫で、なんとも形容しがたい滋味がある。働きバチに印をつけて追いかけ、巣をみつけて掘り出すまでを「スガリ追い」と呼び、狩猟的な楽しみとする地域もある。このような地域では、ハチは幼虫が高価で取引されることも少なくない。
またヒゲナガカワトビケラというトビケラ目の幼虫も食用にされる。とくに長野の一部では(とくにはほかの水生昆虫の幼虫を含め)「ザザムシ」と呼ばれ、季節には専門の猟師があらわれるほどである。
ほかにもたいていの昆虫は食用になるようで、最近では好事家も少なくなく専門書さえ出ている。一部の西洋人は日本人がタコを食べることを驚異の目でみるが、昆虫食を特別視するのはそれと同じ偏見といえるのかもしれない。
それでも昆虫を食べるなど信じられないと思う人もいるかもしれない。しかし、コチニールカイガラムシという南米のサボテンにつくカイガラムシからとれる天然色素は、様々な食品に利用されており、知らずに食べている人も多いはずである。
エジプトのスカラベのように神聖視されるのは特別な例だが、ほかにも南ヨーロッパのセミやテントウムシのように、その姿が愛される例もある。日本人は世界的にみても昆虫の好きな民族で、世界最古の昆虫小説として「堤中納言物語」の「虫めづる姫君」のような物語もあるほどである。
また小泉八雲ことラフカディオ=ハーンは日本人が日常的に虫の声を楽しんでいることに注目している。私が子どものころまで、東京の祭の縁日には虫の屋台が出ており、スズムシやマツムシ、キリギリスをはじめ、様々な鳴く虫を売っていた。
私の祖母も毎年スズムシを飼養し、その声を楽しんでいた。またいわずもがな、カブトムシやクワガタムシのなかまは、虫好きな子どもたちの最高の遊び相手であり、憧れである。夏休みに網を振り回して虫を捕る子どもが大勢いて、どこでも虫網を売っているのは、世界広しといえども日本だけである。
残念なことに、このような昆虫に対する子どもの興味は成長とともに薄れてしまうことが多く、大人になってまで虫を追いかけている人は稀である。これもまた周囲に何でも合せてしまいがちな日本人の習性なのかもしれない。
また残酷ととらえる風潮もあるためか、昔のように夏休みの宿題で昆虫の標本を提出することも少なくなってしまったようだ。その一方で、近年は昆虫を愛でる人々の裾野が広がりつつある。
男ばかりだった昆虫研究者にも女の人が増えてきているし、単純に興味として昆虫が好きになったり、少年時代の情熱に回帰する大人も増えてきている。昆虫の造形の美しさに着目した芸術家も増えつつあり、昆虫をモチーフにした作品を専門とする人も少なくない。
大人になってから昆虫を愛でる気持ちは、おそらく子どものときの情熱とは異なり、一時的なものではないだろう。孤独に昆虫に対する愛情を温めてきた私のような者には、同好の士が増えているようで、とても嬉しい昨今である。
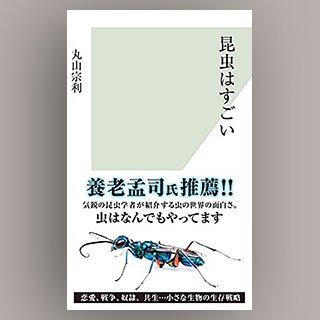
丸山宗利(まるやま むねとし)
1974年、東京都生まれ。北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。大学院修了後、日本学術振興会の特別研究員として3年間国立科学博物館に勤務。2006年から1年間、同会の海外特別研究員として米・シカゴのフィールド自然史博物館に在籍。2008年から九州大学総合研究博物館助教、2017年から准教授。
アリやシロアリと共生する好蟻性昆虫を専門とし、アジアでは第一人者。国内外での昆虫調査を精力的に実施し、数々の新種を発見。農学博士。昆虫学者。シカゴ在任中に深度合成写真撮影法と出会い、現在、研究のかたわら様々な昆虫を撮影。主な著書に「ツノゼミ ありえない虫」(幻冬舎)、「森と水辺の甲虫誌」(編著、東海大学出版会)、「アリの巣をめぐる冒険」(共著、同上)、「アリの巣の生きもの図鑑」(共著、同上)などがある。







