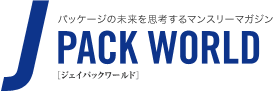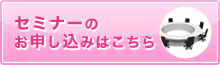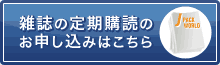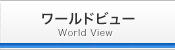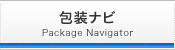トップページ > World View
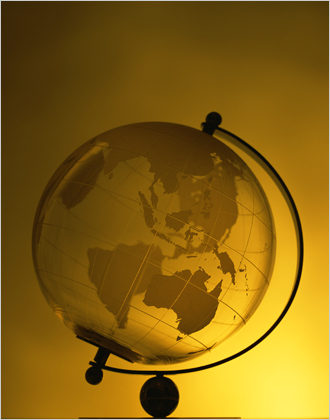
2007年のユーキャン新語・流行語大賞に、「空気が読めない」の略語「KY」がノミネートされたときは心を痛めたが、2025年はT&D保険グループ新語・流行語大賞に、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」が選ばれた。
「働くこと」も「初の女性首相の誕生」も嬉しいことには違いないが、高市首相の「働いて働いて働いて働いて働いて」には、どことなく自虐的な響きが漂う。
円安や物価高騰、災害、異常気象など時代変化の寒波に晒されている国民のなかには、歌人・石川啄木の和歌「働けど働けど猶わが生活(くらし)楽にならざりぢつと手を見る」が身につまされる人もいよう。高市首相の思いや心意気はかうが、「働いて働いて猶民の生活楽にならざり」では済まない。
高市首相肝いりの物価高対策をはじめとした総合経済対策はいいが、国民の年越しにはいずれの手当も間に合わぬようだ。ただ前政権時代に決定した「年収の壁」(130万円→160万円)の引き上げのみが実施されるのは真に皮肉なことではあるまいか。
「令和」の年号の由来となる歌集「万葉集」には、有名な仁徳天皇の「高き屋に登りて見れば煙立つ民のかまどはにぎはひにけり」との和歌が載せられている。積極財政も大事だが要は「心」である。心が無ければ何も動かない。
今回は、政治学者の中島岳志氏の著書「縄文 革命とナショナリズム」(太田出版)の「南島とヤポネシア」のなかから一部を紹介したい。ときには深く日本人の「根っこ」について考えてみるのもいい。
* * *
島尾敏雄は1961年、「ヤポネシアの根っこ」という文章を発表した。彼はここで、「日本や日本人が何であるかと知りたいという思い」が「私をとらえてはなさない」といい、その基層を南方に求めた。
島尾は、これまでの日本人論は大陸からの影響にばかり目が向けられてきたことに疑問を投げかけた上で、自らの直観として、南太平洋に開かれた南方とのつながりを感じずにはいられないと述べる。
海を越えた南の方から働きかける深いところからの呼びかけが感受される(島尾1973b:66)。
島尾は「覆おうとして覆うことのできない海からの誘いが、足もとの方から立ち昇ってくる」と述べる(島尾1973b:66)。彼の足もとにあるのは、奄美の大地であり、南方の島々である。この足もとから、南の島々とのつながりが立ち昇ってくるという。
彼は奄美での生活で、根源的な体験をくり返してきたという。それは「民謡の旋律や集団の踊りの身のこなし、会釈の仕方とことばの発声法等」に表れた「複合の生活リズム」であり、そこには大陸の影響では語れない土着性がある。
それは異国のそれではなく、本土ではもう見ることは困難になってしまったとしても、遠くはなれた記憶のなかで一つに結びつくような感応をもっているとしか思えないものだ(島尾1973b:66)。
島尾は、ここに日本の「もうひとつの顔」を見出す。奄美をはじめとした「南島」には、日本列島に生きる人びとの「根っこ」の部分が残っており、それが「遠く離れた記憶」を呼び醒ます。そして、その「感応」のなかにこそ、日本人の本質へと至る「手がかり」があるのではないかと提起する。
頭からおさえつけて滲透するのではなく、足うらの方から這い上がってくる生活の根のようなもの。この島々の辺りは大陸からの鱗に覆われることが薄く、土と海の匂いを残していて、大陸の抑圧を受けることが浅かったのではないか(島尾1973b:67)。
島尾は、南島の土着性のなかに、南太平洋の島々と連なる「深層」を見出す。それは「足のうらの方から這い上がってくる生活の根のようなもの」であり、頭で理解する大陸由来の日本とは異なる。足裏で感じる「深層」は南島と連続性のなかにあり、この連なりを「ヤポネシア」と名付けてみたいという。
おそらく三つの弓なりの花飾りで組み合わされたヤポネシアの姿がはっきり表れてくるだろう。そのイメージは私を鼓舞する。奄美はヤポネシア解明の一つの重要な手がかりをもっていそうだ(島尾1973b:67)。
その地帯(沖縄や奄美、先島を含めた地域-引用者)にヤポネシアの根っこが残っていると考えることは、大きな見当はずれではなかろう。そして日本の、南太平洋の島々の一つのグループとしての面を考えることは、かたくしこってしまった肩のぐりぐりをもみほぐしてくれるに違いない(島尾1973b:67-68)。
島尾は、ここで日本を「広大な太平洋の南の辺りに散らばった島々の群れつどいのなか」に位置付けた。そして、沖縄や奄美の島々にこそ「ヤポネシアの根っこ」が残っていると論じた。重要なのは「根っこ」という表現である。
彼は、「根っこ」を失った現代日本を批判し、その一方で「根っこ」を残す南島への回帰を訴えた。これは「ヤポネシア」という空間論であるとともに、「根っこ」という時間論でもある。日本の深層は、大陸からの影響などによって隠され、表層には姿を表わさない。
しかし、その「根っこ」には、共通する土着性が潜んでいる。現代日本は、そのことに無自覚だが、南島には、生活のなかに「根っこ」が息づいている。「根っこ」は、ミクロネシアやポリネシアと繋がるものであり、かつ太古の歴史と繋がるものである。
島尾のヴィジョンは、徐々に輪郭を帯び、南島と古代が結びついていった。彼は、1962年6月13日に「私の見た奄美」という講演を行っているが、ここでは「ヤポネシア論」が空間論ではなく、時間論として構想されていることが明確になっている。
島尾は「日本のなかには、ある固さがある」と感じるという。それは日本人全体に共有されている「やわらかな、なにか」がある(島尾1973b:81)。島尾は「固さ」の一つに「武士道」があるのではないかと提起する。しかし、武士道は「日本民族が本来持っていたものではなく、途中からでき上ってきたもののような気が」する。中国の儒教や禅宗などの影響によって構成されたものであって、日本の深層にあるものではない(島尾1973b:82)。この「固さ」が南島にはないと、島尾は抑える。この認識が、南島の生活と古代の連続性につながっていく。
奄美は武士道的なものを素通りしてきた。大陸からの影響を大きく受けず、文化の基層を生活や精神のなかに残してきた。奄美は「古い、大むかしの状態から中世、近世の充実なしにいきなり近代に入ってきたようなところ」がある(島尾1973b:83)。
古い時代の状態が、近代に入ってまで持ち越されたのではないかということを、文学的に感じているのです(島尾1973b:82)。
現在は「古い時代」のものを「野蛮」ととらえがちである。時代が新しくなると、文明が進歩し、生活が改善されていくと見なされている。歴史の授業では「古い時代」を否定的にとらえ、克服の対象としてきた。古代人には「人間らしい気持ちなどない」と理解されてきた。
しかし、この見方はおかしいのではないか。現代人のおごりがここに表れているのではないか(島尾1973b:83-84)。島尾は、南島に残っている「深層」を掴み直すことのなかに、現代文明の問題を克服する手がかりがあるのではないか示唆する。
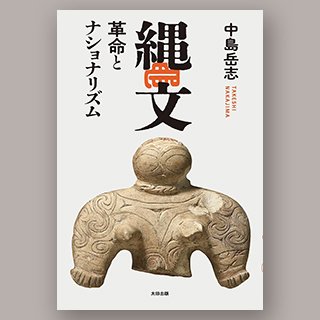
中島岳志(なかじま たけし)
1975年、大阪府生まれ。1999年に大阪外国語大学(現・大阪公立大学)外国語学部ヒンディー語専攻卒業し、2004年に京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究・研究科博士課程修了。2005年に「中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義」で、大佛次郎論壇賞とアジア・太平洋賞大賞を受賞する。2007年に日本南アジア学会賞を受賞。
京都大学人文科学研究所研修員、ハーバード大学南アジア研究所客員研究員、北海道大学公共政策大学院准教授を経て、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教として研究・執筆活動を展開。著書に「秋葉原事件 加藤智大の軌跡」「血盟団事件」「親鸞と日本主義」「超国家主義 煩悶する青年とナショナリズム」「自民党 価値とリスクのマトリクス」「思いがけず利他」などがある。