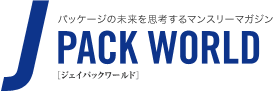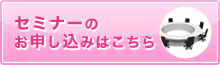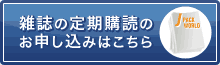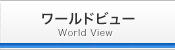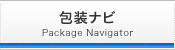トップページ > World View
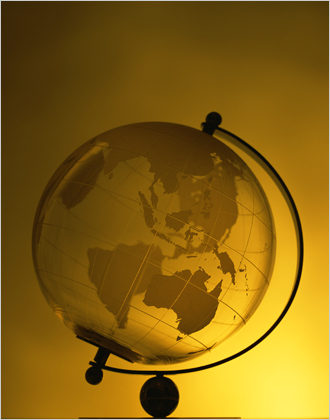
2026年明けから、世界を騒然とさせるドナルド・トランプ米大統領の発言や行動に関するニュースが絶えない。また「国益にならない」などとし、31の国連機関を含む66の国際機関や条約からの脱退や資金拠出の停止を指示する大統領覚書に署名したとのニュースである。
国際的な枠組み「パリ協定」の前提となる国連気候変動枠組み条約や国連人口基金なども含まれているようだ。米国はすでに「パリ協定」からの離脱を表明しており、気候変動枠組み条約から脱退すると、条約事務局の運営や途上国支援の資金繰りなどの悪化も懸念される。
無理が通れば道理が引っ込むような世界であってはなるまい。「気候変動枠組み」などは一国も欠けてはならぬ世界の問題である。否、世界が「泣く子と地頭には勝てぬ」と傍観を決め込むようなら、それが問題だ。悪事を為すことと、(黙諾し)悪事に抗しないことは同じである。
むしろ悪事に抗しないことを悪事とは思わず、善事であるかのように解して平気でいることが、世界の常識となることの方が問題である。明治の教育者の言葉を借りれば「悪の敵になり得る勇者でなければ善の友とはなり得ない。利害に目が暗み、善悪の識別のできないものにリーダーの資格はない」である。
戦後、身近な教育者の豹変ぶりに失望し、歴史に日本人の神髄を求めた作家なども珍しくない。キリスト教思想家の内村鑑三氏の著作「代表的日本人」の西郷隆盛と上杉鷹山と二宮尊徳と中江藤樹と日蓮を一人ずつ作品として描いた作家もいる。
今回は、哲学者の梅原猛氏の著作「日本文化論 」(講談社学術文庫)から一部を紹介したい。「徒然草」「方丈記」および著者の吉田兼好や鴨長明への評価は真に稚拙だが、国語教育における真摯な思いには大いに共感する。
* * *
日本を考えるとき、日本一国のみで考えて始末しようとしても、おそらくそれはだめで、やはり日本を考えるには世界全体を考えねばならない。つまり、日本文化を考えるにも、世界文化とのつながりにおいて考えないとだめだろうということですが、その世界の文化というものを考えるには、いったいどう考えたらよいのか、そういうことからまず考えていかないと、とても日本の文化というものは考えられないだろうと思うのです。
ところで今の世界文化を考える視点として、一番正しい視点を与えているのは、イギリスの歴史家トインビーではないかと思います。これは皆さんご存じでしょうが、彼は1956年には日本へも来まして、私も会いましたが、彼が画期的な歴史家だということは否定できません。
なぜ画期的かといいますと、従来のギリシャ・ヨーロッパの歴史家というものは、ヨーロッパの歴史だけを世界の歴史だと考えた。ギリシャ・ローマにはじまり、近代ヨーロッパに伝わる、あの歴史だけを歴史そのものと考えたのに対し、トインビーは、むしろ世界の歴史は実は複数である、ヨーロッパの歴史というものは、ただ世界の歴史の一つに過ぎないというふうに考えた。
つまり世界の歴史を、ヨーロッパの歴史をその一つとするような複数の文明の歴史という考えを彼がはじめて提出した、といってもさしつかえないのではないかと思うからです。トインビーは現代の世界を次のように観ています。
十六世紀から十九世紀までの世界の歴史は、ヨーロッパが、その文明―ヨーロッパが発明した科学技術文明―を使って、世界を一つにした時代である。その意味において、ヨーロッパの文明が世界を征服した時代だ。これが十六世紀から二十世紀初めにかけての歴史の動向ではないか。
ところが、どうやらその歴史は一つの壁にぶつかっている。二十世紀後半からは、おそらく別の歴史がはじまるに違いない。その歴史というものは、どういう歴史かというと、今までヨーロッパ文明に征服されていたほかの各文明が、ヨーロッパ文明に反撃を開始する時期が来ている。そういう歴史が次の二十世紀以降の世界史の大きな同行であるに違いない。
このような歴史の視点は、今のわれわれが歴史を考える場合、あらゆるほかの歴史観に比較して、もっとも正しい歴史観であると私は思います。もちろん、これだけで世界の歴史を割り切ることはできないのですが、少なくともこれは今後の世界を考える上において、どうしても欠くことのできない一つの観点ではないかと思うのです。
日本人というものは、大昔は神道だったかもしれないが、聖徳太子以来仏教を採り入れ、それによって文化を発展させてきました。そういうふうに文化を発展させてきた日本人の精神的努力を積極的に評価せずに、日本の文化を語ることはできないと思います。
そういう日本人の精神の糧が、明治以来ほとんど教育から姿を消してしまっていることを注意せざるをえません。たとえば、国語の問題一つとってみましても、国語というものが日本の学校で教えられる時間そのものが大変少ない。国語教育とは、何よりも日本語に対する愛情を育てるものです。
フランスの文化は日本に比べたら、むしろ歴史的に浅いのです。十世紀ごろのフランスはまだ野蛮人でした。日本は十一世紀初期にはもう「源氏物語」をもっています。それなのに、日本では国語の時間はフランスよりも少ない。それ以上に、日本人の精神的バックボーンを形成した親鸞・道元・日蓮ら、こういう人たちについて、教育において、いったいわれわれは教えられたでしょうか。
こういうのが国語教育にはほとんどはいってきません。そして国語教育は、たとえば戦前は「徒然草」とか「方丈記」というようなものが中心で、旧制高校の入試試験でも「徒然草」「方丈記」「枕草子」が国語の試験の中心でした。
私は「徒然草」「方丈記」が、必ずしもつまらぬとはいいませんが、「徒然草」にしても「つれづれなるままに」でしょう。退屈なるにつれて、です。「方丈記」―無常でしょう。退屈男と無常男。これは少なくとも一流の人物ではないと思います。
吉田兼好にしても鴨長明にしても、それぞれ面白い人物ですが、けして歴史を動かすような人物ではありません。やはり第一級の文学者ではないと思います。第一級の人物は、退屈とか無常とかいう感情におぼれていないと思います。
日本史上には、もっと激しい理想や情熱をもった人がたくさんいます。親鸞は、おそらく退屈などしないでしょう。彼はいつも、自分の罪業の深さの嘆きと、同時に、自分のような人間でも救済されたという信仰の喜び、この二つの感情に支配されたはなはだ充実した人生を生きていました。
ですから、「歎異抄」もいいですが、親鸞の「和讃」や「教行信証」もぜひお読みください。これを読むと、親鸞がどういう人かわかりますが、非常にまじめな、自己反省の深い人でした。そして、そういう著書で自己の嘆きの深さと仏に救われた信仰の喜びを歌い上げています。私は、日本歴史のなかで稀にみる真実な人間だと思うのです。
それから日蓮がおります。日蓮の文章もなかなかいい。日蓮は日本の民衆にもっとも人気のある宗教家ですが、おそらく日蓮の情熱に人びとは打たれるのだと思います。それはものすごい情熱です。日蓮の手紙は実に上手で面白い。女の人には女にふさわしいことを書いている。
男の人には男にふさわしいことを書いている。みんなどこかに泣き所があって、誰でも日蓮さんにいかれてしまう。くだいていえば、日蓮はラブレターの名人です。日蓮には片一方に強いところがあり、片一方には涙もろい、ほろりとするところがあって、いまだに日本人の心を魅了し、日本を動かしているのです。
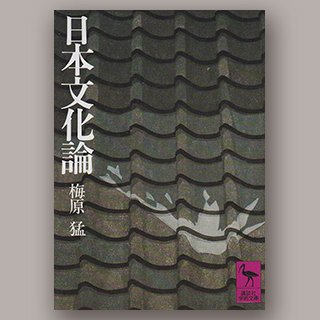
梅原 猛(うめはら たけし)
1925年、宮城県生まれ、京都大学を卒業後、文部省特別研究生を経て龍谷大学の非常勤講師から専任講師、次いで立命館大学文学部に就職、講師、助教授、教授を歴任。大学紛争で職を辞したのち、京都市立芸術大学美術学部教授に就任する。
同大学の校舎統合にともなう移転問題に取組む中で学長に就任し、1980年代には「国際日本文化研究センター(仮称)創設準備室」の室長として国際日本文化研究センターの創設に尽力、設立後に所長に就任。実存哲学の研究に取組み、そののち「梅原日本学」と呼ばれる独自の世界を開拓した。
ほかにも「スーパー歌舞伎」「スーパー能」の創作など、幅広い活動を行い、これら業績が評価され、文化功労者に選出、のちに文化勲章を受章した。京都市立芸術大学名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授、京都市名誉市民の称号を贈られる。2019年1月、肺炎のため93歳で死去。叙従三位、著書に「隠された十字架一法隆寺論」「葬られた王朝一古代出雲の謎を解く」「親鸞『四つの謎』を解く」など多数。